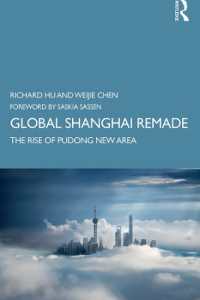内容説明
タイ、フィリピン、インドネシアにおける国家の成立過程の精細な分析と「比較」を通してナショナリズムの起源・性質・将来を理論的・実証的に探究し、ナショナリズムの深層論理を明らかにする待望の労作。
目次
第1部 ナショナリズムの長い弧(ナショナリズム、アイデンティティ、系列性の論理;レプリカ、アウラ、後期ナショナリズムの想像力 ほか)
第2部 東南アジア各国研究(暗黒の時代、光の時代;専門的な=専門家の夢―二つのジャワ古典に関する考察 ほか)
第3部 東南アジア比較研究(東南アジアの選挙;共産主義後のラディカリズム ほか)
第4部 なにが残されたか(不幸な国;ネーションの善性)
著者等紹介
アンダーソン,ベネディクト[アンダーソン,ベネディクト][Anderson,Benedict]
1936年、中国昆明生まれ。コーネル大学名誉教授(政治学・国際研究)。ケンブリッジ大学(古典)を卒業後、アメリカに渡りコーネル大学で東南アジア地域研究を修める。インドネシア政治文化研究において地歩を固めたものの、1965年のいわゆる9月30日事件を機に成立したスハルト政権を批判し、インドネシアへの入国を禁止される。これを契機に研究対象をタイ、フィリピンに拡げ、1983年には、現在では新古典とも評価される『想像の共同体』を発表し、アジア研究、政治研究、ナショナリズム研究のみならず、歴史研究、文学研究にも衝撃を与えた
糟谷啓介[カスヤケイスケ]
1955年生まれ。一橋大学大学院言語社会研究科教授。専門は言語社会学、言語思想史
高地薫[コウチカオル]
1971年生まれ。東京大学東洋文化研究所研究員。専門はインドネシア政治史
イヨンスク[イヨンスク]
一橋大学大学院言語社会研究科教授、博士(社会学)。専門は社会言語学
鈴木俊弘[スズキトシヒロ]
1972年生、一橋大学大学院言語社会研究科博士後期課程在籍。専門はフィンランド学、フィンランド近代史・移民史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
-
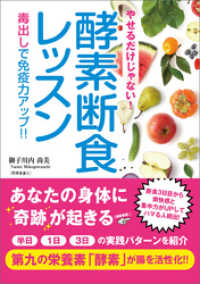
- 電子書籍
- 酵素断食レッスン
-
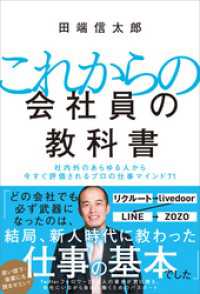
- 電子書籍
- これからの会社員の教科書 社内外のあら…