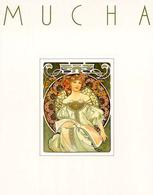内容説明
インド哲学を元とし、ギリシャ哲学にも通じる日本初の哲学書が今日の言葉によって甦る。
目次
1 自然と共生するための道具「言語」―基本理念(共生のための五つの“はたらき”―仏教用語「五智」;共生する四つの“すがた”―仏教用語「四身」)
2 声と語意によって世界のすがたを表現する道具「言語」―言語とは何か(論題;論題の応用解釈)
3 仏典にみる言語論(インドラの文典“梵語”;表音文字)
4 物質と生物の“はたらき”と“すがた”を表現する(「声」の響きは物質と同調している;ヒト科社会の十種の“すがた”―仏教用語「十界」 ほか)
著者等紹介
北尾克三郎[キタオカツサブロウ]
1943年京都に生まれる。浪速短期大学(現大阪芸術大学短期大学部)デザイン美術科。大阪文学学校詩型科に学ぶ。1967年にアメリカ大陸横断旅行。その後、設計、環境デザイン、まちづくり、教育に従事。仏教哲学をライフワークとする(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。