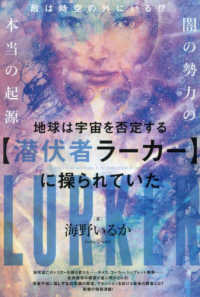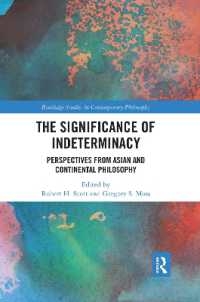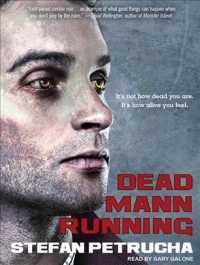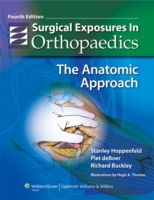内容説明
宮城・石巻に生まれ、仙台藩雪荷派・免許皆伝の旧制二高師範、「人間を造る」弓道を唱え、多くの門人を導いた“弓聖”の物語。
目次
第1章 阿波研造の伝記(生い立ち;石巻で武術を習うこと ほか)
第2章 阿波研造の遺産(研造の門人たち;オイゲン・ヘリゲルと鈴木大拙 ほか)
附録1 阿波研造の遺文―「阿波範士言行録稿本」抜粋(「阿波範士言行録稿本」について;講話録「大射道」 ほか)
付録2 仙台藩雪荷派―「仙台藩当流射芸史」(樋口臥龍原作)より(平塚籾右衛門重次;仙台藩雪荷派の継承)
著者等紹介
池沢幹彦[イケザワミキヒコ]
昭和11年7月栃木県生まれ。昭和40年3月東北大学理学研究科卒業(理学博士)。4月東北大学理学部物理学科助手、助教授を経て昭和63年11月東北大学科学計測研究所教授。平成12年3月定年退職(東北大学名誉教授)。弓道履歴:昭和37年4月上田正康範士の指導で弓道を始める。昭和56年6月東北大学学友会弓道部副部長、部長(平成7年迄)。平成22年4月宮城県弓道連盟副会長(弓道教士六段)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
ishi_game
1
印象ですが,現代「弓道」への影響は大きいものがあるみたいですね.問題は適正な指導者を欠いた状態で理念だけが広く末端に浸透して生き残ってしまったということでしょうか.2015/12/07
きのこ
1
現在の弓道とは環境等多く違うとはいえ、読んでいて反省させられること多々あり。本当に達人とは見ている世界が違うのだなと思う。射法についての記述がないとのことだが、知りたいと思うがそれもまた未熟といわれるのかも.... 自分の今までの稽古はあまいと反省2013/10/23
uruga130
1
ヘリゲルが書いた弓道関連の本はどれも弓を媒介とした“禅”をテーマにし限定されていましたが、これは阿波師範が経験を通して目ざした“弓”の“道”について書かれています。阿波師範が目ざして行ってきた、弓道の意味の変遷や歴史などは弓道をやっている人にはとても興味深く、もっと深いレベルを意識して自分も弓の稽古をしてみようかな?という気持ちにさせられる。阿波師範のように“射の道”を通して自分を造り上げていく指導ができる人が今は居ないだけに、やはりこの人は“弓の神”だと思いました。2013/05/17
さんつきくん
1
武術としての弓術に「禅」の趣を取り入れる画期的な手法で、近代弓道の礎を築いた阿波研造師範。技術よりも弓道を通し、禅を学ぶことで「弓禅一味」などの人を造る弓道は様々な人々に影響を与えた伝説人。有名な暗闇の中で、線香を目掛けて放った矢は的中し、二発目はその尾に当たったエピソードはドイツ人哲学者エリベル氏を虜にした。1880年宮城県桃生郡大川村横川(現石巻市河北町)出身。東日本大震災で児童数十名が亡くなられた大川小学校は母校とされる。石巻地方2013/02/22