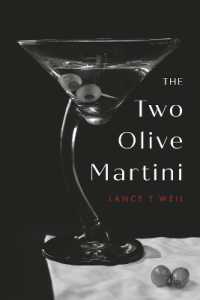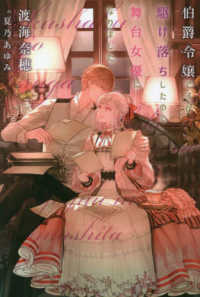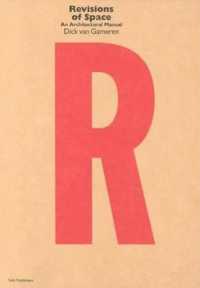内容説明
東京電力福島第一原発20km圏内。野に咲く花が、命をつなぐ。2013年から福島に移り住み、原発周辺の町で花を生けて歩いた一人の華道家の魂の記録。
目次
作品
文章(人と花;そこに花を生けること;花の世へ、花の野へ)
著者等紹介
片桐功敦[カタギリアツノブ]
華道家。1973年大阪生まれ。1997年24歳で大阪府堺市のいけばな流、花道みささぎ流家元を襲名。そのいけばなのスタイルは伝統から現代美術的なアプローチまで幅広く、異分野の作家とのコラボレーションも多数。小さな野草から、長年のテーマでもある桜を用いた大規模ないけばなまで、その作品群はいけばなが源流として持つ「アニミズム」的な側面を掘り下げ、花を通して空間を生み出している(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ゆう
29
少し前に読んだ「性食考」の中で言及されていた本。「生け花」のイケと「生け贄」のイケが同じ語根であることに、揺さぶられるような衝撃を受けた。これらは同じ根をもつものなのだ。意識の深い所から立ち上がってくるその実感は、本書を読んでますます確かなものとなる。本写真集の著者は、大阪出身の華道家元。震災後の福島で彼は一つ一つの場そのものを器とするように、花を生ける。生と死、自然と人工、生け贄と鎮魂。そのあわいにあるのは祈りの言葉。日本人は無宗教であると言われるが、だとしたらこの感覚はどこからきているものなのだろう。2020/04/07
たまきら
16
恒例・友人のジェホさんの個展を見に行き、福田さんから素敵な本を見せてもらった。だんなと二人で見入る。福島の野の花のたくましさ、そしてはかなさ。自然の力に圧倒された。エリザベスに贈ってあげたい。2016/10/11
散歩牛
4
本屋でざっとめくって思わず買ってしまった。2013年に福島で居住した一人の華道家の作品集。もともと私は華道がよくわからない。花器に溢れる花を見ても特に何も感想が出ない。でもこの写真集の花からは目が離せなかった。花は命なんだと初めて感じた。鎮魂は形をもって現れるのだと思った。誰もいない砂浜に一本だけ立っている白百合。荒れ果てた家内のタンスの上に置かれた小さな花瓶の小さな野菊。雑草だらけの港にぽつんと残った、ひしゃげた車の中からあふれる沢山の野花。巻末に書かれた題名の由来も含め、色々な思いが溢れる1冊でした。2016/02/21
ゴロチビ
2
赤坂憲雄の本から。震災の被災地に行き、そこにある器にそこにある花を活ける。その事実だけで他に説明は要らない気もした。とても強い"力"を感じた。「活け花」の本なので偶々近くの棚に中川幸夫の本があり、そのせいかいくつかの作品にちょっとだけ中川幸夫を感じてしまった。純粋な美だ。ページには「花」「採取地」「器」等の説明があり、ミソハギが禊萩、ヒメジオンが姫紫苑であることを久しぶりに思い出した。植物には本来美しい名前があるのにカタカナ表記に慣れ切っていたのだ。水葵の復活は自然と人間の関係を象徴してるようで興味深い。2022/04/14
Qfwfq
0
★4.52020/01/19