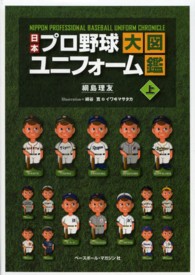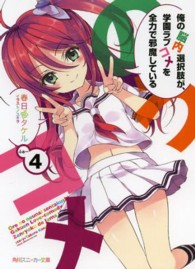内容説明
年中参詣、行事暦、寺社めぐり、そして祭り。「鰯の頭も信心から…。」江戸庶民の精神安定剤。旅は遊山か信仰か、御利益求めて何処までも。
目次
序 鰯の頭も信心から
第1章 伊勢屋稲荷に―江戸の流行神
第2章 すたすた坊主の来るときは―宗教者・門付け芸能者
第3章 今日は観音、明日は不動―年中参詣・行事暦
第4章 大江戸寺社めぐり―鐘は上野も浅草も
第5章 神仏見参―居開帳と出開帳
第6章 旅は遊山か信仰か―御利益求めて何処までも
第7章 神輿担いでワッショイショイ―江戸の祭り
著者等紹介
山路興造[ヤマジコウゾウ]
1939年東京渋谷に生まれ、少年時代を日本橋で暮らす。早稲田大学で芸能史・民俗芸能を学ぶ。30代の終わりに京都に遷り、「京都市史」の編さんに携わり、京都市歴史資料館長などを務める(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ヴェネツィア
270
江戸の人たちは信心深いといえば、まあそうだ。ただし、どこまでが信仰心で、どこからがそれに名を借りたお祭り騒ぎや遊興であったのかは微妙なところだ。本書は浮世絵を手掛かりに、そうした江戸庶民たちの信仰の事情を探ろうという試み。まずは、遊行の宗教者や門付け芸能者の多いこと。西鶴をはじめとした文学作品にも多数登場する。次いでは、江戸のあちこちで寺社がらみの年中行事の多いこと。それだけ江戸市中には神社仏閣も多かったのだ。ことに多いのが「伊勢屋稲荷に犬の○○」と言われるように稲荷社だろう。また、庶民信仰は⇒2025/07/02
ナツ
3
オールカラーで、浮世絵を見ながら江戸時代の庶民の信仰について解説。神頼みしながらも楽しみつつ一年が過ぎていく様子が羨ましくもある!2019/10/28
kunugi
2
江戸の流行神、特に稲荷の流行った過程などを知りたいと思ってたまたま手に取った本だったけれど、他の話題も十分にインパクトがあった。わいわい天王って何だよ! とか、すたすた坊主があまりにもキタキタ親父にしか見えないとか、突っ込み所が満載である。江戸の信仰事情を眺めていると、信仰の持つ経済的・観光的な側面が浮き彫りになって面白い。2010/09/02
マイケル・タクマ・ヤン
1
江戸時代の信仰に係る行事などの絵図を紹介している。ほぼ図説で分かりやすい。ざっと眺めるには良い。信仰と祭り、商売は縁が切れないものなのだという感想を持った。迷信と切って捨てる必要はない。これだけ人と財を動かすのだから。それは今も変わっていないように思う。2025/06/29