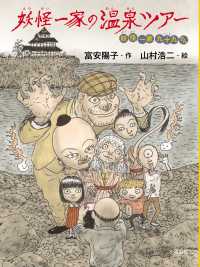内容説明
名編集長として出版界に知られてきた著者が文芸の世界に氾濫するおかしな文章や言葉遣いを指摘しつつ、かつて文士たちがいかに優れた文章を書くことに腐心してきたかを編集者の視点から綴った書。
目次
第1章 日本語の乱れている現状(印刷物には間違いがないという信仰;文学者も間違った日本語を書くとは ほか)
第2章 ある力によって変えられた日本語(終戦後使えなくなった言葉;支那という呼称 ほか)
第3章 なぜ日本語は乱れてきたのか(失われた恥の感覚;ら抜き言葉は日本語の乱れか ほか)
第4章 正しく、美しく、強い文章―文士はどういう努力をして来たか(文章についての三つの戒律;記号を使うな、オノマトペを使うな ほか)
著者等紹介
大久保房男[オオクボフサオ]
大正10年9月1日紀州熊野に生れる。慶應義塾大学国文科に学び、折口信夫に師事。学徒出陣で海軍予備学生となり、終戦により復学し、昭和21年9月卒業。同年11月講談社に入社し、「群像」編集部に入る。30年より41年まで同誌編集長。著書に小説『海のまつりごと』(藝術選奨文部大臣新人賞)など(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
-
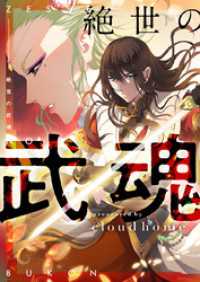
- 電子書籍
- 絶世の武魂【タテヨミ】第188話 pi…
-
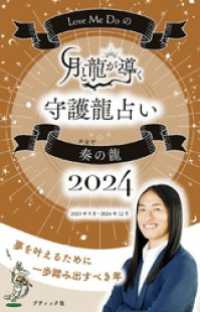
- 電子書籍
- Love Me Doの月と龍が導く守護…