出版社内容情報
気鋭の英文学者らが論じた幻想文学の本格的な研究・批評の集成『幻想と怪奇の英文学』第2弾!
ジョイス『ダブリン市民』の「姉妹」新訳や、編者2名が平井呈一の再評価を促す対談も収める。
前口上【東雅夫】
第1部:ゴースト・イン・リテラチュア
・姉妹【ジェイムズ・ジョイス】【下楠昌哉(訳・解説)】
・薔薇十字会員の亡霊を降ろす/祓うこと―ジョイス「姉妹」の改稿とイェイツへの応答【田多良俊樹】
・乱世のなかに夢幻を描く―英国に渡った郡虎彦と『義朝記』【鈴木暁世】
・『フランケンシュタイン』の幽霊―伝承バラッドの再話として【小川公代】
・「ぼくらはまた逢うだろう」―『コルシカの兄弟』における幽霊の〈声〉と〈すがた〉【岩田美喜】
・フィラデルフィアの幽霊屋敷―マット・ジョンソンの『ラヴィング・デイ』における混血(ムラートー)アイデンティティの呪縛と解放【白川恵子】
第2部:幻獣/変身/テクノロジー
・甦る鳥たち―古代中世ヨーロッパにおける鷲とフェニックスの描写【大沼由布】
・クエスティング・ビーストの探求―トマス・マロリーの不思議な動物【小宮真樹子】
・スフィンクスの笑み―H・G・ウェルズ『タイムマシン』と人間の未来【遠藤徹】
・或るモノとの遭遇―解剖/化学劇場の『ジキル博士とハイド氏』(仮)【石井有希子】
・複写する機械は人間の夢を見るか?―ジェイムズ・ジョイス「複写」『ダブリン市民』(仮)【桃尾美佳】
・重なり合わない分身と分心―ウィリアム・シャープと尾崎翠の「こほろぎ嬢」をめぐって【有元志保】
・ラジオの描くモンスター―ルイス・マクニースの『ダークタワー』と大衆の問題【川島健】
・赤ずきんはなぜ狼になったのか―アンジェラ・カーター「狼三部作」【高橋路子】
・鴉の娘の「新しいおとぎ話」―オードリー・ニッフェネガー『レイヴン・ガール』【金谷益道】
第3部:災疫のなかの奇跡
・中世ヨーロッパの教訓的例話集にみるイノセントな子供たち―『アルファベット順逸話集』の奇蹟譚【小川真理】
・悪、破局、そして笑い―災害の物語としてのジェイムズ・ホッグ『男の三つの危険』【金津和美】
・崇高の向こう側―コーマック・マッカーシー『ザ・ロード』【山口和彦】
・時空をかける女たち―ルース・オゼキの『有る時の物語』【臼井雅美】
東雅夫[ヒガシマサオ]
下楠昌哉[シモクスマサヤ]
内容説明
気鋭の文学者らが論じた幻想文学の本格的な研究・批評の集成、第2弾!ジョイス『ダブリン市民』の「姉妹」新訳や、翻訳家・平井呈一の偉業をめぐる対談も収める。
目次
第1部 ゴースト・イン・リテラチュア(ジェイムズ・ジョイス「姉妹」の翻訳;薔薇十字会員の亡霊を降ろす/祓うこと―ジョイス「姉妹」の改稿とイェイツへの応答;乱世のなかに夢幻を描く―英国に渡った郡虎彦と『義朝記』 ほか)
第2部 幻獣/変身/テクノロジー(甦る鳥たち―古代中世ヨーロッパにおける鷲とフェニックスの描写;クエスティング・ビーストの探求―トマス・マロリーの不思議な動物;スフィンクスの笑み―H.G.ウェルズ『タイムマシン』と人間の未来 ほか)
第3部 災疫のなかの奇跡(中世ヨーロッパの教訓的例話集にみるイノセントな子供たち―『アルファベット順逸話集』の奇蹟譚;悪、破局、そして笑い―災害の物語としてのジェイムズ・ホッグ『男の三つの危険』;崇高の向こう側―コーマック・マッカーシー『ザ・ロード』 ほか)
対談 幻想と怪奇の匠・平井綴一の足跡を追って―東雅夫×下楠昌哉
著者等紹介
東雅夫[ヒガシマサオ]
神奈川県生まれ。アンソロジスト、文芸評論家。元『幻想文学』編集長、現『幽』編集長。著作に『遠野物語と怪談の時代』(角川選書、第64回日本推理作家協会賞受賞)など
下楠昌哉[シモクスマサヤ]
東京都生まれ。同志社大学文学部教授、博士(文学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
fantamys
満月
-
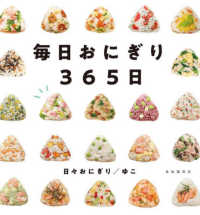
- 和書
- 毎日おにぎり365日


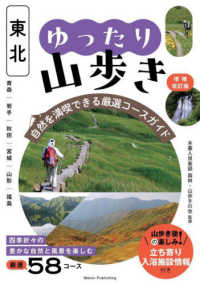

![Karte von DEUTSCHLAND - 1920 [gerollt] : Deutsches Reich - Weimarer Republik (2020. 1 S. 70 x 85 cm)](../images/goods/ar/work/imgdatak/39596/3959664796.jpg)


