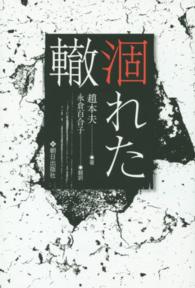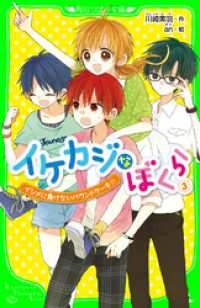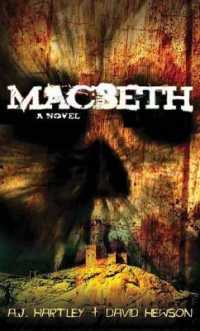内容説明
ヒトが人になるためには幾つもの越えなければならない節目がある。そこに民俗の知恵が籠められている。産育儀礼に見るいのちの受け渡し。
目次
人とは
子供はどこから
天菩薩―髪の民俗
仮親
義理と人情
福子・福助
胞衣
まなざし
犬卒塔婆
嬰児籠〔ほか〕
著者等紹介
佐野賢治[サノケンジ]
1950年、静岡県生まれ。筑波大学大学院歴史人類学研究科修了後、愛知大学・筑波大学教員を経て、神奈川大学大学院歴史民俗資料学研究科教授、日本常民文化研究所所長、国際常民文化研究機構運営委員長。比較民俗研究会を主宰するほか日本民具学会会長、野外文化教育学会副会長などを務め、地域振興、野外文化教育活動の実践に取り組む。文学博士(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
うえ
9
「「お疱瘡の御神様は踊りは好きでござる 踊りを踊ればお疱瘡が軽ござる」鹿児島県川内市に伝わる疱瘡踊りの歌の一節である。南薩摩地方は疱瘡神信仰が盛んな土地で、疱瘡が流行ると伊勢の神を迎えたり、春彼岸を中心に疱瘡の神とされる虚空蔵菩薩の祠に団子を供えたりした。伊勢の神が疱瘡神と考えられたのは、最も神威が高い神なので、最も恐ろしい流行病である疱瘡のイメージと重ねられ、逆転の発想により踊りや歌で歓心を買い、味方に付けることによって一度は罹らねばならない疱瘡をできるだけ軽く済まそうとする民衆の苦肉の策といえた。」2019/07/03
鵜殿篤
0
【要約】人間が「大人になる」までの成長過程に関わるトピックを連ねた、民俗学のエッセイ集。高度経済成長の過程で急激に失われていった様々な日本の習俗を、柔らかい筆致で蘇らせ、読んでいて温かな気持ちになる本だ。2017/04/25