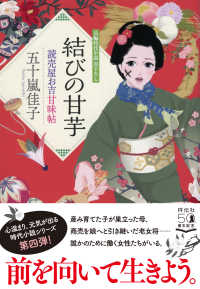内容説明
現代の英米哲学とハイデガーを接続。『存在と時間』の不整合を指摘しつつ、後期思想につながる精髄をえぐり出す。ハイデガーの概念は、いま何を明らかにするのか。
目次
第1部 ハイデガーの心の哲学(世界内存在、開示性、理解;理解、ふるまい、テクネー;日常性の心の哲学)
第2部 ハイデガーの言語哲学(ロゴスと「として」構造;有意味性、道具、語り;真理と有意味性;世界‐言語‐人間)
著者等紹介
荒畑靖宏[アラハタヤスヒロ]
1971年東京都生まれ。1994年慶應義塾大学法学部政治学科卒業。2006年フライブルク大学哲学科博士課程修了(Ph.D.)。現在、成城大学文芸学部専任講師(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
有智 麻耶
3
荒畑靖宏は、ハイデガー『存在と時間』が抱える不整合——とりわけ「真理」概念の解釈をめぐる問題を、後期思想の観点から解消し、チャールズ・テイラーのいう「HHH」の伝統や、現代の英米哲学と接続していく。すべてを理解できたわけではないが、ときに神秘的とさえいわれるハイデガーの言語論が、かなりとっつきやすいものに感じられるようになった。古荘真敬の研究を読むことで、詩的言語よりの解釈について理解を深めたい。2025/02/24
Seita
0
ハイデガーの真理論とウィトゲンシュタインの蝶番論の類似性を指摘している箇所が印象的だった(第六章)。この類似性が成り立ち、かつ、それにハイデガーのロゴス論を加えるなら、「本質認識」の次元は、知識と理解と意味を可能とする条件に重なるとのことであった。ウィトゲンシュタインを援用することで、晦渋なハイデガーの議論の見通しが良くなったのは確かだが、知識と理解と意味の条件が、同一次元に同居できているということが、うまく掴めなかった。2017/09/13
-

- 電子書籍
- 大君として生きよ【タテヨミ】第59話 …
-

- 和書
- 淡彩いつも心に野の花を