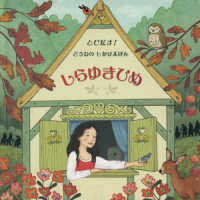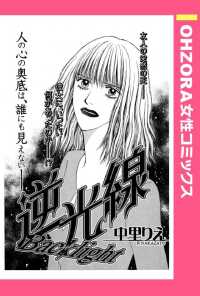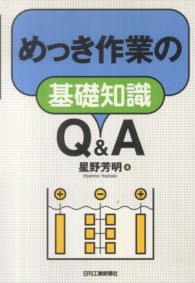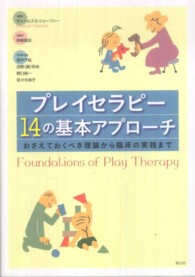目次
プリミティヴ・フューチャー
NETWORK BY WALK
家であり、同時に都市である
部分と部分との関係性による新しい秩序
森の中に開かれた「弱い建築」
「曖昧な領域としての建築」の試み
部分の建築
曖昧さの住宅 住むための地形
「あいだ」を顕在化する
ひとつの形・いくつものかかわり〔ほか〕
著者等紹介
藤本壮介[フジモトソウスケ]
1971年北海道生まれ。1994年東京大学工学部建築学科卒業。2000年藤本壮介建築設計事務所設立。現在東京大学特任准教授、慶應義塾大学、東京理科大学非常勤講師。主な作品「伊達の援護寮」(2003、JIA新人賞、AR AWARDS入賞)。「安中環境アートフォーラム国際設計競技」(2003、最優秀賞)。「T house」(2005、東京建築士会住宅建築賞金賞、AR AWARDS入賞)。くまもとアートポリス設計競技「次世代モクバン」(2005、最優秀賞)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ネオジム坊
2
知的かつ詩人な、モノを考えようとしている若手建築家、藤本壮介の本。藤森テルボが彼を「ル・トロネ修道院を『光の凝固』と表現した男」というように、感性の言語表現に長け、特にコルビュジェへの表敬が深い。ロンシャンの教会のことを「完全に人間が作ったものでありながら、ずっと太古の昔から存在していたような」という。ただこの本が出たということは、「言葉」はあまりにも魅力的なのだが、その言葉に実直すぎる建築は、とても魅力的と成り得ないことを示唆しているのかもしれない。特に論理にこだわり過ぎてやめられないのは、悲劇だ。2012/04/21
かずとよ
1
とてもわかりやすい、ことばで書かれており、また、作者の建築に対する情熱や愛情が飾らない言葉で綴られている。著名な方だが、偉ぶらなく謙虚な姿勢がよくわかる。いいものを作る人はよき鑑賞者であると思った。しかし建築本のUserの数ってほんとに少ないな。もっと興味がある人が増えればいいのに。2012/11/20
A
1
建築を設計する過程において、言葉と形は相互に作用し合いながら発展していく。そのためある一つの言葉はいろいろな意味を帯び、またその意味は動的に変化していくのだが、藤本さんは特にそのことが顕著だと思う。だから藤本さんの文章はどこか曖昧で掴み所がないものになっている。そしてその曖昧さは、藤本建築それ自体の表現の特徴にもなっているように感じる。2011/01/30
Ksaka
0
言葉やダイアグラムを手掛かりに思考を可能な限り抽象的な建築にする手法はとても興味深かった。ただ高円寺の住宅や大学の図書館を見るとそのやり方が本当良いのかは疑問が残る。特に住宅としては住みこなしにくいようなものが多いように思う。あいだの建築、という考えは都市デザインにも応用できるな。(lanewayとかもそんな印象)2012/10/04
Yu Yamaji
0
★★★ [未分化建築] 現代→機械化された建築 未来→未分化された建築 未分化=プリミティブ