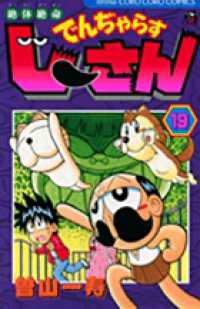内容説明
我々は建物の完成や品質や作品性にこだわりすぎていないか。建築の本懐はその誕生ではなく、時代と共に生きていく時間の中にこそあるはずではないか。渾身の問題提起の書。
目次
1章 建築のちからをめぐって(建築の力―地球の裏側から考える;建築に何が可能か―三五年目の建築論 ほか)
2章 建築の広がりをめぐって(都市戦略としてのデザイン;都市再生は駅再生から ほか)
3章 建築の言葉をめぐって(建築に思想はあるか;よそゆき超高層は不要 ほか)
4章 人のちからをめぐって(篠原修の居る風景;「山」と「家」 ほか)
著者等紹介
内藤廣[ナイトウヒロシ]
1950年横浜生まれ。74年早稲田大学理工学部建築学科卒業。74‐76年同大学院にて吉阪隆正に師事、修士課程修了。76‐78年フェルナンド・イゲーラス建築設計事務所勤務(マドリッド)。79‐81年菊竹清訓建築設計事務所勤務。81年内藤廣建築設計事務所設立。2001年東京大学大学院工学系研究科社会基盤学専攻助教授。03年同大学大学院教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
お芋
2
初めて建築家の本をの読み終えた。 私自身が建築ではなくインテリアだからか、完全に面白かったとは言えないのが本音だが、勉強になる箇所は多かった。 勉強になった箇所だけ抜き出してリストアップしたので、今後の課題に活かしていきたい。2021/10/06
tsumizeKa
1
内藤廣による雑誌等への寄稿を集めたもの。書かれた内容はバラバラであるが、氏の建築、土木、都市に対する考え方は一貫している。建築も長命だが、一見畑違いに思える土木に関わるようになり更に長いスパンで建築を考えるようになった。関わっている人間の人生を遥に超えた先のことを考えること。今やっていることが10年、20年そして100年後にどんな姿になっているか。そういった真摯な姿勢はどんな職能にも必要なんだろうなとおもった。2013/11/11
TTM
0
吉阪さん、菊竹さんの話が印象的に残っている。だいぶ前に読んだので、もう一度読み直したい。
おこ
0
内藤さんの考え方を知っていくにつれて、建築に対する作品的な考えが変わってくる。竣工すればそれは建物として作品のひとつになるのであろうが、できるまでは建築として見続けなければならないと思う。動詞としての建築は、あらゆる概念を繋いで現物化する過程のことを言うのではないか。この建物はどういう建物かと聞かれた時に、ストラクチャーとかマテリアルとかじゃなくて、抽象的な表現、安らぐだとか引き締まるだとか、そんな言葉が出てくるものこそが作品性とは逆の表現の成果になるのではないかと思う。2018/05/29