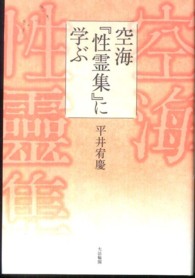内容説明
“近代‐前近代”“西洋‐非西洋”“都市‐農村”の二項対立にとどまりつづける都市研究。本書は、ロゴス的な都市学の限界を突破して、レンマ的な“あいだ”を開く新たな人間環境学の誕生を告げる。12名の論者が集い、今日の都市問題に多彩な光を投げかける。
目次
第1部 “あいだ”を開くために(日本的ソーシャルワークと“あいだ”の論理;宗教的ケアの理念と現実―「臨床宗教師」の制度化へ;公益法人を運営するということ―“脱中心化”と“再中心化”に即して;“縁”の倫理;建築とまちのリノベーション;持続可能な縮小都市の“かたち”―グローバル化時代の都市モデル模索)
第2部 “かたち”の論理(パリの景観保全―「ピトレスク」をめぐって;琉球の都市と村落―集落の形成思想をめぐって;古代ギリシャの民主制と理性―都市の思想の源流;関一と「大大阪」―田園都市思想の実践;田舎家の“縁”―再発見・再利用された民家;ユネスコ学習都市構想の社会学)
著者等紹介
木岡伸夫[キオカノブオ]
1951年、奈良県に生まれる。京都大学で哲学を専攻、大学院D.C.退学後、大阪府立大学総合科学部(9年間在職)を経て、1997年から関西大学に勤務、教授として現在に至る。学生時代に専攻したベルクソンの「生の哲学」をベースに、地球環境危機が浮上してきた20世紀末からは、人と自然、人と人の関係性を考える、最も広い意味での環境哲学を、ライフワークとして手がけてきた。2002年度の在外研修において、パリEHESS(フランス国立社会科学高等研究院)でオギュスタン・ベルクに師事。以後、和辻哲郎が切り拓いてベルクの継承した風土学の理論構築を、自身の課題として引き受け、その完成にこぎつけた(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。