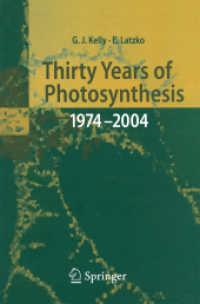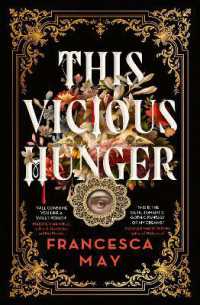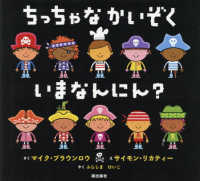内容説明
広松の志をつぐ者は結局何になればよいのか。近代の超克者になるしかないのである。没後10年、広松渉をめぐる「実践派」荒岱介の新解釈。
目次
第1章 広松渉はどんな思想家だったか
第2章 共和制への移行が日本を救う
第3章 二人の広松
第4章 知を増せば悩みと哀しみは増す
第5章 近代を超克するのは環境革命
第6章 広松はプラトン主義に自覚的だったか?
第7章 21世紀はマルチチュード運動
第8章 シンポジウム『東北アジアと広松渉』
附論(東北アジアを歴史の主役に;日本人は縄文人と渡来系弥生人のハイブリッド)
著者等紹介
荒岱介[アラタイスケ]
1945年生。社会運動家。早稲田大学在学中から学生運動に参加、1970年代には三里塚闘争、東大闘争で実刑判決を受け下獄。社会主義学生同盟委員長などを経てブントを主宰。近年は広松渉との交流をつうじて現代思想を研究。出版社、印刷会社を経営するかたわら環境保護運動を行う
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
den55
0
2011年に亡くなった元ブント委員長、荒氏が後半生、研究に没頭した広松渉とその思想の解説。広松は日本でのマルクス研究において重要人物だが、その思想は分かり難い部分が多く、この書は広松理解のための好著と言うべきである。論及は戦前の42年の「近代の超克」から始まる。そしてマルクス「改釈」(広松の造語)から、関係性を経て環境問題まで至り、現代に至っての欧米近代の行き詰まりから、主題とも言うべき「東亜の新体制」へと繋がる。西欧生産主義的にマルクスを読み神学に陥らせないという広松のマルクスへの情熱。面白い一冊だ。2018/01/08