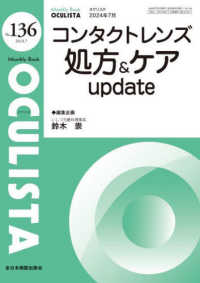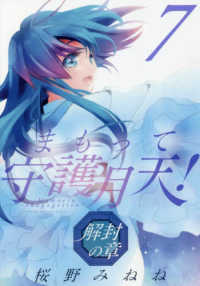出版社内容情報
植物バイオテクノロジーの最新情報が満載!!
植物は太陽電池を備えた生産工場
食糧・エネルギー・資源・環境問題……
21世紀、植物で地球を守ろう
発刊によせて
バイオサイエンス、バイオテクノロジーがゲノムからポストゲノム時代に入った。多くの生物種の
全遺伝子構造が明らかになりつつある現在、生命科学は全遺伝子の機能を解明し人類の福祉と
健康に役立てる方向に動いている。植物においても遺伝子の構造と機能が分かれば、人為的に
代謝経路を作成、改変する代謝工学が可能である。地球上の生命の根源は、太陽エネルギーを
利用して、無機物から有機物を作る植物の光合成反応にある。この植物の機能の解明とその活
用が、近未来の食糧生産、植物による工業原料生産、環境修復・浄化などにきわめて重要であ
る。本書編纂の意図は、こうした観点から植物代謝工学の現状と将来を総括的に網羅し、代謝工
学によって植物に何が期待できるかを紹介しようとするものである。
本書の構成は、植物代謝工学の重要性を序論で説き、第1章では世界の植物資源の現状、地
球環境はどこまで悪化しているのか、それが植物にはどう影響しているかを導入部分とした。第2
章では植物の代謝を人為的に改良するために、それぞれの素反応がどこまで明らかになったか
に触れ、植物生理学の教科書的な記述ではなく、素反応のどこを改良することが重要であるかを
論じた。第3章では植物代謝工学に必要なゲノムからプロテオーム、メタボロームへと進みつつ
ある科学・技術の最先端を紹介し、植物における現況にも言及した。第4章では、植物代謝工学
の食糧増産への期待、とくにストレス耐性付与による植物の生産性向上の試みを紹介した。第5
章では、化石資源に依存しない循環型社会の構築には植物代謝工学が鍵になるとの視点から、
経済産業省のプロジェクトが目指す、植物による工業原料生産に焦点を当てた。そして第6章で
は、環境浄化、修復に植物はどのように貢献できるかを述べた。植物は緑の肝臓ともいわれ、
数々の汚染物質を浄化する能力がある。第7章では、あらゆる科学技術がそうであるように、新
技術には未経験のリスクも懸念される。植物バイオテクノロジーが含んでいる陰の部分は何か、
それをいかに取り除くか、リスクとベネフィットの考え方を述べ、将来展望とした。
植物バイオテクノロジーの最新情報を網羅するために、わが国の第一線で活躍中の多くの研
究者に、一部は米国の学者にも、執筆をお願いし、きわめて短期間で完成に漕ぎ着けた。それは
現在の科学・技術は余りにも進歩が速く、できるだけ最前線の情報を読者に伝えたいとの執筆者
全員の思いからである。化石資源に全面的に依存している現在の文明は大きな転換を迫られて
いる。本書に何度か登場する、「植物の代謝工学を強力に推進しなければ地球上の炭素の循環
系は戻ってこない」との主張は監修・編集者そして執筆者全員の一致するところである。年間、地
球上の全植物が固定する太陽エネルギーは世界の化石資源エネルギー消費量の10倍もある。
植物の能力を平均10%上昇させ、化石資源に相当する工業原料、燃料に利用することは夢では
ない。植物が固定した炭素を利用すれば、それから生じる二酸化炭素は植物が再び固定する。
炭素の循環系は19世紀までの人類が行ってきたことである。21世紀以降の子孫に緑の地球を引
き継ぐ責任は、20世紀を謳歌してきたわれわれ全てにある。植物は太陽電池を備えた生産工場
である。何を生産するかは工場に据え付ける機械、すなわち遺伝子、代謝経路次第であり、しか
もこの工場は老朽化すれば堆肥に戻る生分解性の工場である。「植物は理想のバイオリアクタ
ー」である。本書から是非とも植物への期待と可能性とを読み取っていただきたい。
植物バイオテクノロジーの最新の全貌を著した書は類をみない。植物の基礎、開発研究に直接
携わっている研究者、学生諸氏には、本書から植物代謝工学の全貌を見ていただくと共に、この
科学技術の発展のために御意見、御助言を頂ければ幸甚である。さらには食糧、エネルギー、
資源、環境問題に携わっている方々、関心をお持ちの方々には、本書を通して植物の重要性に
是非とも目を向けていただきたい。石油化学文明が大きな転換期を迎えようとしているが、植物バ
イオテクノロジーの研究者、技術者だけでは持続可能な社会の構築など到底達成できない。す
べての国民の理解と同意がなければならない。
今、急速に進歩している植物分子生物学、植物細胞工学の知見に基づき、「植物代謝工学ハン
ドブック」を編纂することはまさに時にかなった試みであると確信する。その成果は必ず政府機
関、企業、若手研究者そして社会全般に植物の可能性に理解と認識を与え、21世紀以降の地球
と人類に大きな夢と希望を与えるに違いない。
2002年 6月 監修者 新名 惇彦 吉田 和哉
内容
序 論 植物代謝工学の意義 (新名 惇彦) 1
第1章 植物資源の生産と利用
第1節 食糧および産業に関する植物遺伝資源 (渡邉 和男) 10
第1項 農業の生産性と持続性の問題点 10
1.食糧危機 10
2.食糧の量と質:栄養不足と食品安全性 12
3.環境破壊と天然資源の枯渇 14
4.緑の革命 15
5.品種と遺伝資源 17
第2項 植物遺伝資源と世界 19
1.遺伝資源の重要性 19
2.遺伝資源、バイオテクノロジーと世界 20
3.遺伝資源の保全と植物科学 22
4.遺伝資源の利用とバイオテクノロジー 24
5.最後に 25
第2節 森林資源 (柴田 勝) 28
1.はじめに 28
2.世界における木材、紙パルプの生産量と消費 28
3.紙パルプ原料の品種開発(育種) 30
1)長・短期の育種戦略 31
2)第1段階:量の育種 31
3)第2段階:質の育種 34
4.まとめ 39
第3節 工業用資源 40
第1項 デンプン (中久喜輝夫) 40
1.はじめに 40
2.デンプンの生産量と種類および一般的性質 40
1)デンプンの生産量 40
2)デンプンの種類と一般的性質 42
3.デンプンの生産と加工技術および利用 44
1)デンプンの生産 44
2)デンプンの加工技術と利用 46
4.今後の課題 54
1)新しいデンプンの作出 54
2)デンプンの生分解性プラスチック分野への利用ほか 55
第2項 リグノセルロース (桑原 正章) 57
1.資源とその利用の概要 57
2.リグノセルロースの変換と利用 59
1)全体利用 59
2)成分利用 60
3.おわりに 70
第3項 油脂 (平尾 宗樹) 72
1.はじめに 72
2.生産量および原料生産国 72
3.需要動向 74
4.採油および精製技術 74
5.食用油脂加工技術 75
1)水素添加(硬化) 75
2)エステル交換 75
3)分別 75
6.工業分野への利用 76
1)脂肪酸製造技術 76
2)高級アルコール製造技術 77
3)メチルエステル製造技術 78
4)脂肪酸誘導体とその応用 79
5)高級アルコール誘導体とその応用 80
6)油脂の直接利用 82
7.おわりに 82
第4項 天然ゴム (河原 成元) 84
1.天然ゴムの種類 85
2.天然ゴムの構造と非ゴム成分 88
3.天然ゴムの精製 90
4.天然ゴムの非ゴム成分と物性 91
5.天然ゴムの改質 92
6.高純度天然ゴムの改質 94
7.ゴムの樹の品種改良 95
第5項 繊維 (安倍 俊三/春日部芳久) 97
1.植物および植物由来繊維の種類 97
1)植物繊維 97
2)植物由来繊維 101
2.植物および植物由来繊維の生産量 102
1)植物繊維 102
2)植物由来繊維 102
3.植物および植物由来繊維の用途 105
1)植物繊維 105
2)植物由来繊維 105
4.植物および植物由来繊維の
遺伝子操作 105
1)植物繊維 105
2)植物由来繊維 107
第6項 色素、香料、生薬、タンパク質 (鍋島 成泰) 109
1.はじめに 109
2.色素 109
1)植物色素の種類と原料植物 109
2)植物系食品色素の生産動向 110
3)植物染料の動向 112
4)植物色素の課題 113
3.香料 114
1)植物香料の種類と用途 114
2)フレーバーの動向 115
3)フレグランスの動向 116
4)植物香料の課題 117
4.生薬 117
1)植物生薬の種類と生産量 117
2)植物生薬の課題 119
5.タンパク質 120
1)植物性タンパク質の種類と生産量 120
2)遺伝子組換え植物による動物性タンパク質の生産 120
6.おわりに 122
第4節 未利用バイオマス (鍋島 成泰) 123
1.はじめに 123
2.バイオマスの種類と用途 124
1)バイオマスの種類 124
2)バイオマスの用途 125
3)バイオマスの潜在的存在量 126
3.未利用バイオマスの発生量と利用の現状 127
1)未利用バイオマスの利用と問題点 127
2)廃棄系バイオマスの発生量と再利用の現状 127
3)植物系未利用バイオマスの発生量と再利用の現状 129
4.未利用バイオマスの利用拡大の課題 132
第5節 植生環境 134
第1項 植生の変遷 (富澤 健一) 134
1.はじめに 134
2.植生のタイプと純一次生産量 134
3.熱帯林減少 135
1)熱帯林減少の現状 136
2)熱帯林減少の原因 136
3)熱帯林減少の影響 137
4.酸性雨 138
1)酸性雨生成過程 138
2)酸性雨の影響 138
5.砂漠化 139
1)砂漠化の定義 139
2)砂漠化の現状 140
3)砂漠化の原因 140
6.耕地拡張 141
7.地球温暖化の影響 141
8.植物バイオ育種への提言 142
第2項 土壌劣化 (間藤 徹) 145
1.はじめに 145
2.砂漠化、塩類集積、草原化 146
3.表土流亡、土壌浸食 147
4.土壌への有害物質の蓄積 147
5.地力の低下 148
6.酸性雨 149
第2章 植物代謝工学のための分子改良技術
第1節 ゲノム情報工学 152
第1項 ゲノムプロジェクト (柴田 大輔) 152
1.はじめに 152
2.植物のゲノム解析 153
1)モデル生物のゲノム解読 153
2)ゲノム解読の方法論(原核生物の場合) 153
3)ゲノム解読の方法論(真核生物の場合) 155
4)遺伝子構造予測 156
5)ラン藻のゲノム解読 156
6)シロイヌナズナのゲノム解読 157
7)イネのゲノム解読 159
8)マメ科植物および根粒菌のゲノム解読 159
9)ESTの整備 160
3.ゲノム情報から得られる有用知見 160
4.ゲノム情報利用の展望 161
第2項 トランスクリプトーム解析とDNAマイクロアレイ (安藤 候平/河内 孝之) 164
1.はじめに 164
2.トランスクリプトーム解析の現状 165
1)cDNAのランダムシーケンス法による頻度情報の記録 165
2)ディスプレイ法 166
3)ディファレンシャルハイブリダイゼーション 168
4)定量的PCR 170
3.DNAマイクロアレイ技術の実際 171
1)マイクロアレイ用DNA(プローブDNA)の調製 172
2)RNAサンプルからのターゲットDNAの調製 172
3)マイクロアレイの作製とハイブリダイゼーション 173
4)シグナル検出とスポットの定量 173
5)データ解析 175
4.植物研究分野におけるバイオインフォマティクスの利用とマイクロアレイ研究の展望 176
1)植物分野におけるバイオインフォマティクス関連のWebサイト 177
2)植物研究分野におけるマイクロアレイ研究の展望 177
第3項 遺伝子マッピング (近江戸伸子/福井 希一) 180
1.遺伝子のフィジカルマッピングとその意義 180
1)フィジカルマッピングの意義 180
2)FISH法 180
2.マッピングに必要な染色体地図作製法と各種染色体地図 182
1)画像解析法 182
2)各種染色体地図 183
3.各種FISH法 183
1)多重遺伝子族のマッピング 183
2) 種特異的反復配列のマッピング 184
3)単一コピー遺伝子のマッピング 186
4)マルチカラーFISH (M-FISH)法 187
5)EDF-FISH法 188
6)RCA法による単一塩基対変異の検出 190
4.マッピング技術の応用例 191
1)rDNA多型の検出 191
2)反復配列の変異の検出 192
3)遺伝子の位置関係の検出 193
4)形質転換体における外来遺伝子の検出 193
第2節 遺伝子導入技術 197
第1項 核染色体への外来遺伝子の導入法 (大平 和幸) 197
I.ベクターの種類とマーカー遺伝子 197
1.はじめに 197
2.遺伝子導入法 197
1)直接法 197
2)直接導入法に用いられるベクター 199
3.アグロバクテリウムを媒介として用いる方法 200
4.アグロバクテリウムの感染機構 200
5.アグロバクテリウムの
Tiプラスミド由来ベクター 201
1)中間ベクター 201
2)バイナリーベクター 201
3)選択マーカー遺伝子が除去されるベクター 203
6.アグロバクテリウムの宿主範囲 205
7.選択マーカー遺伝子 206
1)抗生物質または除草剤耐性遺伝子 206
2)薬剤耐性以外のマーカー遺伝子 207
8.問題点と今後の展望 209
II.個体再生技術と代謝工学の対象となる植物 211
1.個体再生技術 211
1)不定芽形成(不定芽誘導法) 211
2)苗条原基法 213
3)不定胚形成(embryogenesis)(不定胚誘導法) 214
4)遺伝子導入による再分化技術 217
5)個体再生技術の形質転換への利用 217
6)再生技術を用いない形質転換法 217
7)再生技術の形質転換への利用 218
2.代謝工学の対象となる植物 218
1)ユーカリ 218
2)ダイズ 222
3)サツマイモ 222
4)イネ 222
5)ゴムの木 223
6)ナタネ 223
3.代謝工学の対象となる代謝経路 223
4.今後の展望 224
第2項 核外小器官への遺伝子導入法 (鹿内 利治) 226
1.オルガネラ形質転換とは 226
2.葉緑体形質転換 227
3.葉緑体逆遺伝学 228
4.光合成機能改変 229
5.母性遺伝 230
6.葉緑体工場 230
7.葉緑体形質転換の現状 231
8.ゲノム安定性に関する課題 232
9.ミトコンドリアゲノムの形質転換 234
第3項 多重遺伝子導入技術 (柴田 大輔) 236
1.はじめに 236
2.交配法による複数遺伝子の導入 236
3.逐次形質転換法 237
4.複数ベクターによる共形質転換法 237
5.単一ベクターによる多重遺伝子導入法 238
1)長鎖DNAを導入する技術 238
2)複数のDNA断片を効率よくベクターに連結する技術の開発 240
6.おわりに 243
第3節 遺伝子発現制御技術 244
第1項 核遺伝子 244
I.有用プロモーター (長屋 進吾/吉田 和哉) 244
1.プロモーターの基本配列 245
2.5’上流シス配列・エンハンサー配列 246
3.有用プロモーターの現状 246
1)構成的高発現プロモーター 246
2)組織特異的プロモーター 247
3)誘導発現プロモーター 248
4.有用プロモーターの単離法 251
5.外来遺伝子発現のポジション効果を抑制する技術 252
1)染色体DNAの高次構造が遺伝子発現に及ぼす影響 252
2)インスレーターの利用 255
3)MARの利用 256
6.外来遺伝子発現のサイレンシング 257
7.おわりに 258
II.翻訳効率 (加藤 晃) 260
1.はじめに 260
2.植物における翻訳機構 260
3.遺伝子の発現を翻訳レベルで高めるアプローチ 261
1)植物ウイルス由来の5’UTR(5’リーダー配列) 261
2)植物の遺伝子由来の5’UTR 262
4.次世代の植物代謝工学につながる技術 265
1)mRNAの安定化 265
2)ポリシストロン(IRES配列) 266
3)ストレス時の翻訳抑制の回避 267
5.今後の展望 268
第2項 貯蔵器官および細胞内小器官(葉緑体)特異的な発現 (加藤 晃) 270
1.はじめに 270
2.バイオリアクターとしての種子 271
3.種子での異種タンパク質蓄積の試み 271
4.種子での異種タンパク質高蓄積の試み 272
5.バイオリアクターとしての葉緑体 273
6.葉緑体での異種タンパク質蓄積の試み 273
1)微生物由来の遺伝子・オペロン 274
2)動物由来の遺伝子・ジスルフィド結合 274
7.葉緑体での工業原料生産の試み 275
8.次世代の葉緑体工学につながる技術 275
第3項 遺伝子発現抑制技術 (佐藤 文彦) 278
1.はじめに 278
2.変異株の単離 278
3.相同配列組換え、トランスポゾンあるいはT-DNAを用いた遺伝子破壊 279
4.アンチセンス法 280
5.コサプレッションとRNAi 281
1)dsRNA発現ベクターの構築 283
2)RNAiと標的の配列 285
3)RNAiの効率 286
4)RNAiの検出 287
5)TGS 287
6.最後に 287
第4項 植物糖鎖工学 (藤山 和仁) 289
1.はじめに 289
1)植物N―結合型糖鎖 289
2)植物O―結合型糖鎖 293
2.植物における糖鎖プロセシング 294
3.植物の分子糖鎖生物学 295
4.植物糖鎖の生理学的役割 296
5.植物糖鎖とアレルギー 297
6.植物糖鎖構造のヒト型化 298
第4節 植物のポストゲノムの動向 305
第1項 植物のプロテオーム解析 (明石 欣也) 305
1.プロテオーム解析とは? 305
2.プロテオーム解析の原理 306
3.植物におけるプロテオーム解析 308
1)葉緑体のプロテオミクス 308
2)植物の分化 309
3)環境応答 309
4.プロテオーム解析の課題と展望 310
第2項 植物のメタボローム解析 (福崎英一郎) 312
1.植物メタボローム解析とは 312
2.メタボローム解析のための分析戦略 313
1)メタボローム解析のための分析に求められる基準 313
2)HPLCおよびGCの一般的特徴 313
3)質量分析(MS)の一般的特徴 314
4)代謝産物分析の実際 315
3.今後の展望 316
第5節 植物の分子改良技術基本特許の状況 (鍋島 成泰) 318
1.植物の分子改良技術 318
1)遺伝子導入技術の現状と課題 319
2)外来遺伝子の発現調節技術の現状と課題 319
3)遺伝子導入細胞の選抜技術の現状と課題 320
2.植物の分子改良技術の基本特許 320
第3章 一次生産向上のための代謝工学
第1節 光エネルギー変換機構 (嶋岡 泰世/三宅 親弘) 328
1.葉緑体構造 328
2.光エネルギー捕捉 329
1)光を捕獲するアンテナ 329
2)クロロフィルの光励起 329
3)クロロフィル蛍光 331
4)光化学系反応中心における反応 331
3.光エネルギーから化学エネルギーへの変換を担う成分 332
1)光化学系II 332
2)プラストキノン 334
3)シトクロムb6/f複合体 334
4)プラストシアニン 335
5)光化学系I 335
6)フェレドキシン 336
7)フェレドキシン―NADP+オキシドレダクターゼ(FNR) 337
8)ATPシンターゼ 337
4.光合成電子伝達反応(非循環的電子伝達反応) 338
5.ATP合成 339
6.チラコイド膜におけるその他の電子伝達反応 339
1)光合成に必要な電子/プロトンの化学量論比 339
2)光化学系Iにおける循環的電子伝達反応 340
3)Qサイクル 340
4)PSIにおける酸素への電子伝達反応(water-water サイクル) 341
7.光エネルギー変換系における代謝制御 344
1)光化学系IIのダウンレギュレーション 344
2)キサントフィルサイクル 345
3)過剰光エネルギー散逸系としてのwater-water サイクル 346
4)シトクロムb6/f複合体による
電子伝達制御 347
5)チオレドキシンによるATPシンターゼの活性制御 347
6)生体内の酸化剤によるATPシンターゼの活性調節 348
8.おわりに 348
第2節 炭素代謝 (横田 明穂) 351
1.はじめに 351
2.光合成における炭素固定・還元系 352
3.生産性におけるRuBisCOの役割 353
1)PCRサイクル酵素の一般的特徴 353
2)RuBisCO 354
4.光呼吸 355
1)光呼吸代謝系 355
2)光呼吸の生理 357
5.C4―経路:CO2同化のための補助経路 358
6.光合成の律速因子と律速解除による生産性向上のためのバイオテクノロジー 360
第3節 窒素代謝 (榊原 均/山谷 知行) 366
1.はじめに 366
2. 硝酸イオンの吸収と輸送 366
3. 硝酸還元 369
4. アンモニウムイオンの吸収 369
5.アンモニア同化 370
6. 硝酸イオンによる遺伝子制御ネットワーク 370
7. 窒素栄養と形態的応答 373
8.アミノ酸代謝 373
9.C3植物とC4植物 374
10. 窒素化合物の輸送・転流 375
11.窒素栄養による遺伝子発現制御 376
12.翻訳後の制御機構 376
13.代謝工学面への応用 378
第4節 ソース・シンク相互作用 (臼田 秀明) 380
1.はじめに 380
2.ソースとシンクの多様性 383
3.ソースでの炭素代謝 384
1)デンプン合成 384
2)ショ糖の合成 386
3)デンプンの分解 386
4)ショ糖・デンプン代謝関連の変異株・アンチセンス形質転換植物を用いた研究 386
4.師管への糖の供給(ローディング) 388
1)アポプラスティックな経路 388
2)シンプラスティックな輸送 388
5.師管内の糖の輸送 389
6.シンク力 389
7.シンクによる師管からの糖の取り出し(アンローディング) 390
1)マメや穀類の種子 390
2)サトウダイコン 391
3)トマトの果実 391
4)ジャガイモ 391
5)トウモロコシやオオムギの
胚乳のデンプン合成 392
6)シンクが多数ある場合 392
7)シンクからソースに変わる葉の場合 392
8)ショ糖の分解 393
8.糖を介したソース・シンク間の情報伝達 393
9.植物の生産性についてのソース・シンクからの展望 394
第5節 微量元素(イオウを含めて)の吸収と代謝 (關谷 次郎) 400
1.はじめに 400
2.イオウ 401
1)植物および環境中のイオウ化合物 401
2)硫酸イオンの吸収と輸送 403
3)硫酸イオンの還元同化とシステイン合成 404
4)メチオニン生合成 405
5)グルタチオン生合成 406
6)そのほかのイオウ化合物 407
7)イオウ栄養と生育 408
3. 鉄 409
1)土壌中の鉄化合物 409
2)鉄の吸収 409
3)鉄の役割 411
4.そのほかの微量元素 412
第4章 ストレス応答機構の分子改良
第1節 塩・乾燥ストレス耐性植物 (仲山 英樹/吉田 和哉) 416
1.植物が受ける塩・乾燥ストレス 416
2.植物の塩・乾燥ストレスに対する適応機構 418
3.塩・乾燥ストレス耐性植物作製のための標的分子 420
4.浸透圧ストレス耐性を賦与する機能分子の改良 421
5.光酸素ストレス耐性を賦与する機能分子の改良 423
6.イオンストレスに対する耐性を賦与する機能分子の改良 424
7.塩・乾燥ストレスの適応応答に関与するシグナル伝達分子の改良 427
8.塩・乾燥ストレス耐性に関与する機能未知のタンパク質分子の改良 429
9.塩・乾燥ストレス耐性植物作製のための今後の戦略 430
第2節 温度ストレスに対する応答と温度ストレス耐性植物 (草野 友延/宮嵜 厚) 434
1.はじめに 434
2.低温ストレスに対する生理応答 434
3.低温ストレスに対する遺伝子レベルでの応答 435
4.低温ストレス応答における情報伝達系 436
5.耐冷性・耐凍性植物の作出 442
6.高温ストレスに対する生理応答 443
1)HSP100 444
2)HSP90 444
3)HSP70 445
4)HSP60 445
5)HSP20 446
7.高温ストレスに対する遺伝子応答とその制御 446
8.高温耐性植物の作出 448
第3節 光・酸素毒耐性植物 (重岡 成/田茂井政宏/吉村 和也) 450
1.はじめに 450
2.AOSの生成 451
1)おもなオルガネラでのAOS生成系 452
2)種々の環境要因のAOS生成に及ぼす影響 453
3.AOSの消去系 454
1)抗酸化物質 457
2)抗酸化酵素 458
3)藻類のAOS消去および
耐性機構 459
4)AOS消去機構のストレス応答性 461
5)AOS消去機構の問題点 461
4.光・酸素毒耐性の強化を目指した形質転換植物 465
1)AOS消去酵素の制御 465
2)抗酸化物質の制御 467
3)その他の代謝系の制御 468
5.遺伝子ターゲティングのストラテジー -今後の展望- 468
1)新たなストレス耐性関連遺伝子の探索と導入 468
2)オルガネラ内での局在化(ミクロターゲティング) 469
3)導入遺伝子の発現制御 470
4)転写後調節機構の改変 470
5)遺伝子発現のシグナル伝達系の改変 470
6)多重遺伝子導入 470
7)耐性植物の評価法の改良 471
6.おわりに 471
第4節 病害虫耐性植物の分子育種 (藤原 正幸/島本 功) 475
1.はじめに 475
2.植物の病害抵抗性について 476
1)過敏感反応 476
2)誘導抵抗性 477
3)抵抗性遺伝子 478
4)PRタンパク質 480
5)ファイトアレキシン 481
3.これまでに導入されてきた遺伝子 481
1)抵抗性遺伝子 481
2)PRタンパク質遺伝子 481
3)リボソーム不活化タンパク質遺伝子 482
4)病原体由来の遺伝子 482
5)抗菌性ペプチド 483
4.新規なアプローチによる形質転換植物 483
1)NPR1遺伝子 484
2)カルモジュリン遺伝子 484
3)病原体誘導型プロモーター:エリシター遺伝子 485
5.耐虫性について 485
1)Bt遺伝子 485
2)プロテアーゼインヒビター 486
3)食害により放出される揮発性シグナル 486
6.これからの病害抵抗性植物の作出 486
7.おわりに 488
第5節 農薬等負荷軽減植物 (大川 秀郎/乾 秀之/今石 浩正) 492
1.はじめに 492
2.除草剤耐性作物 494
3.環境モニタリングおよび
汚染軽減植物 499
1)ダイオキシン受容体(AhR) 499
2)エストロゲン受容体(ER) 501
3)薬物代謝酵素 501
4.薬物代謝型P450分子種の課題 502
第6節 酸性土壌耐性植物 (小山 博之) 504
1.酸性土壌の成因とストレス因子 504
2.アルミニウムストレスと耐性機構 505
1)アルミニウムストレスの概要 505
2)Alの毒性機構と耐性機構 507
3)低リン酸耐性 508
3.有機酸放出機構と有機酸放出能力強化の分子育種戦略 510
1)有機酸放出能力とAlストレス耐性 510
2)有機酸放出における有機酸代謝と有機酸細胞膜輸送 512
3)代謝工学によるクエン酸放出型酸性土壌耐性植物作出戦略 515
4.その他の分子育種ターゲット形質 518
5.おわりに 519
第5章 植物代謝工学の工業生産への応用
第1節 糖質の改良と増産 (安部 淳一) 524
1.はじめに 524
2.デンプンの構造 525
3.デンプンの生合成 529
4.デンプンの改変 532
1)量を変える 532
2)質を変える 532
5.おわりに 535
第2節 セルロース・ヘミセルロース (林 隆久) 537
1.植物多糖類生合成前駆体 537
2.糖ヌクレオチドの代謝と制御 539
3.セルロースの生合成 541
4.カロース(1,3―β―グルカン)の生合成 546
5.キシログルカンの生合成 547
6.キシランの生合成 547
7.グルコマンナンの生合成 548
8.キシログルカンエンドトランスグルコシラーゼ(XET) 549
第3節 リグニン (大宮 泰徳/林 隆久) 551
1.はじめに 551
2.リグニンの分子育種の幕開け 553
3.遺伝子組換えによるリグニン組成の制御 553
4.新しいリグニン生合成経路の発見 555
5.リグニン分子育種の最近の知見 558
6.おわりに 559
第4節 アミノ酸 (Hyeon-Je Cho /室岡 義勝) 561
1.植物のアミノ酸生合成と輸送 561
2.植物によるアミノ酸の生産 562
1)トリプトファン 562
2)リジンの生産 570
3)アスパラギン酸の生産 570
4)メチオニンの蓄積 571
5)トレオニンの蓄積 572
第5節 脂肪酸 (水谷 正子/落合 美佐) 574
1.はじめに 574
2.高等植物における脂質生合成経路 576
1)脂肪酸合成酵素複合体による脂肪酸合成 576
2)2つの経路によるグリセロ脂質生合成 576
3)脂肪酸の不飽和化 578
4)脂肪酸の鎖長延長 578
5)貯蔵脂質の合成 579
3.脂肪酸の質の改変 579
1)ラウリン酸生産ナタネ 579
2)高ステアリン酸含有ナタネ 580
3)高エルカ酸(C22:1)ナタネ 580
4)高オレイン酸生産ダイズ 580
5)高リシノール酸植物 581
6)γ―リノレン酸生産植物 581
7)タンパク質工学によるC18:0-ACP不飽和化酵素の改変 581
8)植物における超長鎖脂肪酸の生産 582
4.高等植物において高度不飽和脂肪酸を生産するための戦略 582
1)真菌類の高度不飽和脂肪酸生合成系 583
2)海洋性細菌やラビリンチュラ類の高度不飽和脂肪酸合成系 584
3)組換え植物による高度不飽和脂肪酸生産の実際 585
5.今後の展望 586
第6節 テルペノイド (福崎英一郎/小林 昭雄) 587
1.はじめに 587
2.テルペノイドの分類 587
3.テルペノイドの生合成 591
1)テルペノイド生合成の流れ 591
2)イソペンテニル二リン酸(IPP)の生合成 591
3)テルペノイド生合成における鎖長延長反応 598
4.おわりに 604
第7節 二次代謝産物 607
第1項 アルカロイド (庄司 翼/橋本 隆) 607
第2項 カロテノイド (三沢 典彦) 614
1.はじめに 614
2.イソプレノイド基本生合成経路 614
3.Erwiniaのカロテノイド生合成遺伝子群の単離と機能解明 614
4.海洋細菌のアスタキサンチン生合成遺伝子群の単離と機能解明 617
5.真正細菌のカロテノイド生合成遺伝子と生合成酵素のプロフィール 619
6.植物のカロテノイド生合成遺伝子と生合成経路 620
7.crtI遺伝子の導入による植物の代謝工学 622
8.crtB遺伝子の導入による植物の代謝工学 623
9.複数遺伝子の導入による植物の代謝工学 624
10.おわりに 625
第8節 酵素・生理活性タンパク質 (寺嶋 正明) 627
1.はじめに 627
2.産業用酵素および
分析用酵素の現状 627
3.バイオ医薬品の現状と開発状況 631
4.遺伝子組換えタンパク質生産システムの比較 631
5.植物による酵素、生理活性タンパク質の生産の現状 634
6.おわりに 639
第9節 花き育種 (間 竜太郎/柴田 道夫) 641
1.はじめに 641
2.遺伝子組換えによる花色の改変 641
1)遺伝子組換えによる花色の改変例 643
2)遺伝子組換えによる青い花の作出 644
3.遺伝子組換えによる花の寿命の延長 647
4.その他の形質の改変 649
1)花型の改変 649
2)草姿の改変 649
3)病虫害抵抗性等 649
5.今後の課題と展望 649
第6章 植物代謝工学の環境浄化、修復への応用
第1節 大気汚染物質 652
第1項 窒素酸化物 (森川 弘道/高橋 美佐) 652
1.なぜ植物利用か ―ある試算の意味するもの 652
2.NOX汚染の現状と環境への影響 653
3.植物に取り込まれたNO2はどのように代謝されるか 657
4.植物のNO2同化能の多様性と遺伝子 662
5.遺伝子操作で同化能を向上させる 665
6.将来の課題:ガス→ガス変換植物 667
7.植物を植えてどれくらいNO2を減らせるか 671
第2項 無機硫黄化合物 (中村 達夫) 675
1.無機硫黄性大気汚染物質に対する植物の抵抗性機構 675
2.遺伝子組換え技術による有害硫黄化合物耐性の付与 677
第2節 重金属汚染土壌―重金属の植物に与える影響と環境修復植物の開発― (鈴木 伸昭
/佐野 浩) 680
1.はじめに 680
2.重金属の役割、生体への影響 682
3.生体内への取り込み、作用 684
4.金属イオンの分配、局在化 685
5.トランスジェニック植物 688
6.まとめ 690
第3節 アルミニウム耐性 (松本 英明) 692
1.酸性土壌とアルミニウム 692
2.アルミニウム毒性 692
1)アルミニウム障害 692
2)根の伸長阻害を受ける部位 693
3)Al集積部位と集積量 693
4)アポプラスト 694
5)原形質膜 695
6)細胞分裂阻害 697
7)カロース 698
3.アルミニウム耐性機構 698
1)アルミニウム排除機構 698
2)細胞内耐性機構 703
3)アルミニウム耐性の遺伝的側面 703
第4節 ファイトレメディエーション(植物による環境浄化) (Michael J. Sadowsky) 707
第5節 富栄養化の防止 (藤田 正憲/森 一博) 713
1. 窒素・リンの排出と富栄養化のメカニズム 713
2.富栄養化対策のための植物浄化施設 714
3.水質浄化植物による富栄養化対策とデータベース化 716
4.収穫した植物の有効利用法の開発 720
5.浄化植物への育種の試み 723
6.植物浄化法の課題 725
第6節 環境植林 (柴田 勝) 728
1. はじめに 728
2. 早成樹種による商業植林 729
3. 環境植林 733
4. 森林の二酸化炭素(CO2)吸収能 734
5.地球におけるCO2濃度の変化 736
6. 森林の公益的機能 738
7. まとめ 740
第7章 植物バイオテクノロジーの将来展望
第1節 リスクアセスメント (佐野 浩) 744
第2節 遺伝子組換え植物の生態系への影響 (橋本 昭栄) 753
第3節 持続可能な社会 (新名 惇彦/佐野 浩) 766
あとがき (吉田 和哉) 777
監修者
新名 惇彦 奈良先端科学技術大学院大学バイオサイエンス研究科教授
吉田 和哉 奈良先端科学技術大学院大学バイオサイエンス研究科助教授
編集委員(五十音順)
佐野 浩 奈良先端科学技術大学院大学遺伝子教育研究センター教授
重岡 成 近畿大学農学部教授
鍋島 成泰 株式会社住化技術情報センター調査グループ主幹研究員
横田 明穂 奈良先端科学技術大学院大学バイオサイエンス研究科教授
-

- 和書
- 走れ、エロス!