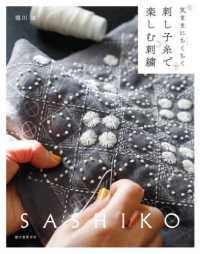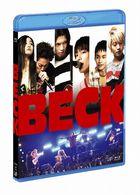出版社内容情報
古来、まよけに最高のものとされる火とそれに連なる赤い色はもちろんのこと、黒色や白色も、桑木やススキや山椒に唐辛子、唾に糞に便所までもがまよけであった。現在では収集の難しくなった各地に伝わるまよけ・厄よけ・病よけの風習を数多く収める。
内容説明
“野”の民俗収集家の集大成。古来、まよけに最高のものとされる火とそれに連なる赤い色はもちろんのこと、黒色や白色も、桑木やススキ、山椒に唐辛子・米・小豆、音や臭い、唾に糞に便所に敷居までもがまよけであった。現在では収集の難しくなった、日本各地に伝わるめずらしいまよけ・厄よけ・病よけの風習を聞き書きの形で収録。好評『まよけの民俗誌』に続く第二集・全49項目。
目次
1 赤ちゃん
2 泣く
3 目篭
4 小豆餅
5 生ぐさ
6 正月
7 衣
8 口つけて飲まぬ
-

- 電子書籍
- ボックスマン~連続殺人の記録~【タテヨ…