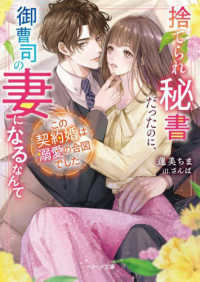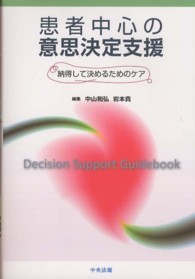内容説明
多和田演劇ワールドの魅力を、実践家と研究者10名が連携し、劇評、演出ノート、作品論、ドキュメント、エッセイ、多和田戯曲の翻訳などで浮き彫りにする。コロナ禍の2020年に思索・執筆された各稿は、閉塞する状況を解き放つ“演劇”そのものの可能性を指し示す。
目次
序 多和田葉子、“世界劇場”という未踏の地平へ
第1部 多和田文学の舞台化をめぐるパノラマ(“劇評”観(光)客はいかにして場違いな0に犯されるか―したための『文字移植』を/から再読する
“演出ノート”漂流する演劇―『動物たちのバベル』創作ドキュメント
“作品論”多和田葉子の戯曲『動物たちのバベル』を読む
“演出ノート”カキタイカラダ―『夜ヒカル鶴の仮面』上演をめぐる断章
“インタビュー”劇団らせん舘に多和田葉子の“演劇”を聞く)
第2部 多和田“演劇”の謎を解く―言葉・声・音楽(“エッセイ”多声社会としての舞台;“エッセイ”レシタティーヴ;“ドキュメント”早稲田大学における多和田葉子&高瀬アキワークショップの歩み)
第3部 多和田戯曲の翻訳と舞台化への模索(東西神話の混交;児童劇の試み)
著者等紹介
谷川道子[タニガワミチコ]
東京外国語大学名誉教授。多和田・ミュラープロジェクト代表者。専門はドイツ現代演劇
谷口幸代[タニグチサチヨ]
お茶の水女子大学准教授。専門は現代日本文学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ユーカ
14
多和田さんの演劇との関係や取り組みは存じ上げなかったので、非常に興味深かった。多和田さんの寄稿もありながら、多和田葉子に関係する演劇プロジェクトにかかわる人々の批評やエッセイ、ドキュメント、そしてドイツ語で書かれた多和田戯曲の日本語訳で構成されている。演劇の中には、戯曲として書かれる台詞と、それが音として役者から発せられる時の距離について、観ていて感じさせられるようなものがあるが、多和田演劇もそうなのだろうなと想像する。ちょっとそういうものから離れていたので、意識して観るものを選んでみようと思った。2021/03/07
-

- 電子書籍
- 地獄祭【フルカラー】【タテヨミ】(20…