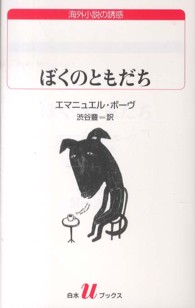出版社内容情報
ラスコー洞窟壁画などを美術批評家・布施英利が息子と訪ねた旅で、人聞はなぜ絵を描くのか?という根源的な問題を思索する。"東京芸大で美術を専攻し、さらに養老孟司の元で解剖学を学んだ美術解剖学のスペシャリスト、数多くの著作もある布施英利は、以前からラスコーなどの壁画群を見て、絵画の根源を探ろうと考えていた。そして2017年夏、美術を専攻する息子を伴い、洞窟絵画を探る旅に出た。日本の古墳壁画や星野道夫のアラスカの写真などと比較しながら、絵画の本質は何かを考察する。旅の記録とその考察が文体を変えて交互に現れ、人はなぜ絵を描くのか?という問題に迫ろうとする。
"
第一日 最も古い絵画 ……明日香村・キトラ古墳壁画へ/ 第1章、夜の語り……旅の準備として「先史時代の洞窟壁画」についての、/ 第二日 ショーヴェ洞窟壁画への旅 ……人類最古の絵画/ 第2章、夜の語り……ネアンデルタール人と絵画の起源をめぐる、/ 第三日 旅の途中 ……中世ロマネスクの村へ/ 第3章、夜の語り……西洋美術の歴史をめぐる、/ 第四日 レゼジー村の洞窟壁画への旅 ……本物の洞窟壁画を見る/ 第4章、夜の語り……写真家・星野道夫のアラスカをめぐる、/ 第五日 ラスコー洞窟壁画への旅 ……ラスコー二とラスコー四/ 第5章、夜の語り……狩猟と解体の世界をめぐる、/ 第六日 パリへ……そして旅の回想/ 最終章、ヒトの絵画の四万年/
布施英利[フセヒデト]
著・文・その他
内容説明
ヒトはなぜ、絵を描くのか?ショーヴェ洞窟壁画、ラスコー洞窟壁画、レゼジー村洞窟壁画群人類最古の絵画を、美術批評家の布施英利が息子と訪ねた二人旅。先史時代の絵画から人間はなぜ絵を描くのかという根源的な問題について、旅の中で思索する。その先に見えた答えとは?
目次
第1日 最も古い絵画―明日香村・キトラ古墳壁画へ
第2日 ショーヴェ洞窟壁画への旅―人類最古の絵画
第3日 旅の途中―中世ロマネスクの村へ
第4日 レゼジー村の洞窟壁画への旅―本物の洞窟壁画を見る
第5日 ラスコー洞窟壁画への旅―ラスコー2とラスコー4
第6日 パリへ―そして旅の回想
著者等紹介
布施英利[フセヒデト]
美術批評家・解剖学者。1960年生まれ。東京藝術大学・美術学部卒業。同大学院博士課程修了(美術解剖学専攻)。学術博士。その後、養老孟司教授の下での東京大学医学部助手(解剖学)などを経て、現在に至る。解剖学と美術が交差する美の理論を探究している。著書は、約50冊(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ぽけっとももんが
リエ
ハチ
アルクシ・ガイ
マサ



![ハラハラどきどきバランスゲーム ころころシーソー [バラエティ]](../images/goods/ar2/web/imgdata2/43447/4344790960.jpg)