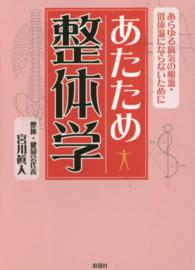内容説明
『出版業界の危機と社会構造』に続いて2007年8月~09年3月までの「出版状況」を、関連する業界の動向を踏まえて、横断的にまとめた後、その危機の実態を分析する。
目次
第1章 出版状況クロニクル承前(二〇〇七年八月;二〇〇七年九月;二〇〇七年一〇月 ほか)
第2章 出版状況クロニクル(二〇〇八年四月一日~五月二〇日;二〇〇八年五月二一日~六月二〇日;二〇〇八年六月二一日~七月二〇日 ほか)
第3章 二〇〇八年出版状況をめぐって(雑誌休刊の問題と新たな出版危機;80年代における書店状況の変化;買切制、委託制をめぐる出版業界の歴史 ほか)
著者等紹介
小田光雄[オダミツオ]
1951年静岡県生まれ。早稲田大学卒業。出版業に携わる(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
minoguchi
3
クロニクルの部分はオンラインでも見ていたのだが、パッケージ化された形で読むと、この1~2年で目に見えて現われてきた(そしてここしばらくはさらに激しくなるであろう)業界の変化を改めて思い知らされる。例えば10年後にこの本を開いてみた時、「本」をめぐる環境はどのような姿になっていて、どんな思いで読むことになるのだろうね。2009/05/09
ISBN vs ASIN vs OPAC
2
真実を暴くオレ様カッケー病は深刻になる一方だが、そんな個人の病状がどうでもよくなるほど、絶望に満ちている。アマゾンが取り扱わない本があると息巻いてたあのばあ様、トーハンが取り扱わない本があるって、知ってたのかね、知らなかったのかね?しかしさ、あのさ、取次不要論みたいなのって、論の一つとしてメジャーになっててもおかしくないと思うんだけど、ないの?それとも、流通における問屋は、どういう形であれ、必要なの?アマゾンが秘密なのはわかったけど、それと同等に、取次は謎のままだ。2016/02/18
笠井康平
1
「自主ゼミしようぜ!」とか言ってるマスコミ志望の就活生にまず読ませたい。2012/02/10
fuchsia
1
一応、中の人なので読んでみた。とはいえ、2008年までの情報なので、電子本関連の情報が皆無だったりと最近の状況変化の激しさを改めて認識させられたりするわけだ。でもって、いまんとこ出版流通に残されたのは減ってるといいつつも販売網なのかなと思ったり。2010/07/04
kozawa
1
オンライン連載から書籍化。出版文化は変わらざるを得ない運命にあるのだろう。本書はその状況の変化のめまぐるしさをみせつける。今の出版が支えている創作をどのように支えていくのか。答えは?2009/07/27
-
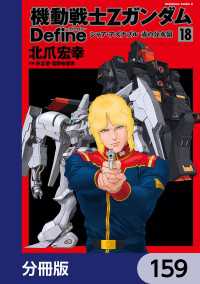
- 電子書籍
- 機動戦士Zガンダム Define【分冊…