内容説明
これまで否定的判断のもと、学術的な検討を欠いてきた“植民地主義”。その“歴史学上”の概念を抽出し、他の諸概念と関連づけ、“近代”に固有な特質を抉り出す。
目次
第1章 “植民地化”と“植民地”
第2章 “植民地主義”と“植民地帝国”
第3章 植民地主義の諸時代
第4章 侵略と抵抗
第5章 植民地国家
第6章 植民地経済の形態
第7章 植民地の社会
第8章 植民地支配と土着文化
第9章 植民地主義の思想
第10章 脱植民地化
著者等紹介
オースタハメル,ユルゲン[オースタハメル,ユルゲン][Osterhammel,J¨urgen]
1951年生まれ。コンスタンツ大学教授。近現代史専攻。ヨーロッパ膨張史、東アジア史に関する著書多数。1989年に刊行されたChina und Weltgesellschaftでドイツ歴史家協会賞を受賞。社会学的な歴史記述が特徴で、帝国主義についても造詣が深い。編著にAsien in der Neuzeit 1500‐1950(1994年)Imperialism and After(共編、1986年)がある
石井良[イシイリョウ]
1931年生まれ。上智大学独文科修了。翻訳家。ドイツ精神史、ナチ時代の抵抗運動、緑の党を含む「第三の道」に関する邦訳のほか、エッセイも執筆(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
spanasu
3
植民地および植民地主義について、その定義、類型、時代区分などを行う。世界各国の事例を、もちろん日本のそれを含めて、考える際に大変参考になることは間違いなく、細かい内容は残念ながら忘れてしまったが興味深い本であった。日本の植民地主義をそれぞれの類型と比較しつつ考えてみたい。2019/11/08
Mealla0v0
3
帝国主義ではなく、植民地主義とはなにか? 著者は多くの事例を、その個々の特殊性を考慮しつつ普遍的な概念として提起していく。植民行為と植民地主義が異なると言う。植民地の伴わない植民や植民なき植民地主義が実際上あり得たからだ。次いで、植民地を支配型・拠点型・移住型と類型化する。軍事支配するだけではなく砲艦外交に始まる市場の独占、武力に支援された入植といったのが各々に当てはまる。他方、植民地国家は本国の延長にはなく、したがってその統治の技法も異なったことも示されていて興味深い。ただ訳文の表記ゆれが結構ストレス。2018/03/16
中桐 伴行
1
勉強会の本。内容の一部に、「他国人による支配は、必ずしも〈不当〉な他国支配と(民族主義が弾頭するまで)考えられていなかった」とあり、もしかしたら色々なタイプの植民地主義が存在するのは、各国の自国民を含めての支配の在り方に起因し、それが遠方の土地であったり、人種の違いにより外見が違ったりするゆえにその支配形態および差別がエスカレートした結果ではなかったのかと思いながら読んだ。僕にはその知見がないため根拠のない仮説でしかないが、社会学的な研究の面白さの一端を見れたような気がした。2024/09/29
無選別ドーナツ
1
ほんまに難しい!!! ただ、植民地とは、植民地主義とは、ということに真っ向から向き合い、丁寧に分析した本は他にないのでは。非常に勉強になりました。2014/05/18
-
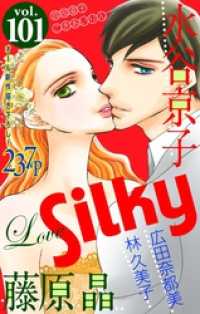
- 電子書籍
- Love Silky Vol.101 …







