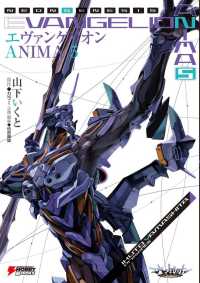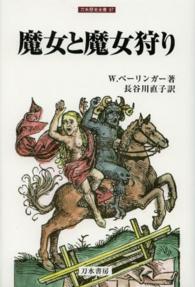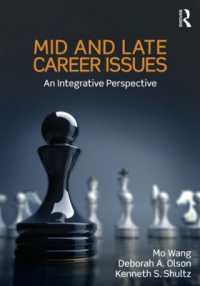内容説明
京都府北部福知山観音寺を訪ね、その作庭現場のフィールドワークから、庭の造形を考え、庭師の生態を観察し、庭のなりたちを記述していく。新感覚の庭園論がここに誕生!
目次
はじめに―ぼくが庭のフィールドワークに出る理由
第1章 石の求めるところにしたがって(庭園の詩学1)
第2章 集団制作の現場から(庭師の知恵1)
第3章 徹底的にかたちを見よ(庭園の詩学2)
第4章 物と者の共同性を縫い上げる(庭師の知恵2)
第5章 庭をかたちづくるもの(庭園の詩学3)
おわりに―フィールドワークは終わらない
著者等紹介
山内朋樹[ヤマウチトモキ]
1978年兵庫県生まれ。京都教育大学教員、庭師。専門は美学。在学中に庭師のアルバイトをはじめ研究の傍ら独立。庭のかたちの論理を物体の配置や作庭プロセスの分析から明らかにするフィールドワークをおこなっている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
- 評価
本屋のカガヤの本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
秋 眉雄
22
大学教員であり、庭師であり、『デレク・ジャーマンの庭』の訳者でもある山内朋樹さんによる、とあるお寺の庭が創り変えられていく工程、そのフィールドワークを記録した一冊。とにかく現場の話。写真の撮り方、映画の撮り方、絵画の描き方、コンセプトアルバムが造られていく様、それらなんかとまったく同じ様に語られていく技術論だとか現場論。わらしべ長者が虻を藁に括り付けたことをDIYとして考え、あるいは藁を庭造りの現場で使われる単なる糸・ひも・縄などと同じものとして見るということ。⇒2025/09/17
kuukazoo
15
京都福知山の古刹・観音寺の作庭現場の観察を通して、庭の構成要素である庭石や木々はなぜこうなっているのかを考察。著者は美学研究者で庭師。ほぼ石組の構成とか配置についての話に、庭師の仕事(道具や体の使い方)についての話も挿入される。作庭を任された庭師の古川氏は事前に設計や工程を決めずかなり即興的に作業を行うことにまず驚いた。そんなことが可能なのか。石組の詳しい話はよく分からなかったが、人の知覚を誘う構成とか配置の話は美術や舞台、公共空間にも共通するので面白かった。作為をどこまで消すかという美意識も興味深い。2024/02/16
die_Stimme
8
美学を専門とする教員でありながらも庭師という肩書も持つ著者が、石庭が作られていくさまをフィールドワークして、一つの石が置かれるにあたってもそこで何が意図され実際に何が起きているかを具に記述していく。庭園を作るにあたって設計図はなく、現場を指揮する一人の庭師とその他の作業員の庭師の共同作業の中で、一手ごとに庭の持つ意味が変わり、そのたびに次の一手が構想される。今までにないタイプ読書経験でとても面白く刺激的ではあるのだけど、だからこそとにかく目が滑る笑。難解な言葉が使われているわけではまったくないのだけど…2024/04/22
僕素朴
4
面白かった!料理のレシピみたいに庭作りを過程から読み解く本。庭師さんの言葉と動きを手掛かりに、古典『作庭記』をときどき参照し、筆者がじわじわと考察を進める。石や植物はゆっくり変化していくから持続的に手入れしてこその庭。でも表面だけ去年と同じサイズに刈り込んでも木は厳密には同じ姿にならない。ゆっくりと形を変えていってしまう。すごいものを相手にする仕事なのだ。作庭に設計図はない。思うような石や木はないから、場所と素材を見て「作ってみて」決める。重機は極力使わない。重機の制約に人間が従わされてしまうから。→2024/02/10
ふん
3
作らないで作る。これはなにか創作をする多くの人にとっては、いつか突き当たり、試行錯誤を強いられる問題に思われます。ブライアン・イーノの音楽、濱口竜介の映画などに通ずるものがあるかもと思いながら読んでいましたが、生活ぜんぶの話に応用してもよさそう。読み終えて、まわりを見れば、トースターがあり、冷蔵庫があり、窓があり、ゴミ箱がある。2025/08/11