内容説明
28のキーワードで学ぶポピュラー音楽研究の基礎から最前線まで。ジェンダー、人種、階級、ジャンル、法、アニメ、シティ、アマチュアリズム…幅広いキーワードと現代的な事例から、音楽文化を考え、常識を問い直す!
目次
第1章 基礎編―ポピュラー音楽を支える概念(ポピュラー;テクノロジー;コマーシャリズム/キャピタリズム ほか)
第2部 事例編―論点としてのポピュラー音楽(ジャンル;法;文字 ほか)
第3部 拡張編―異分野との交差と新展開(ビデオゲーム;ファッション;アニメ ほか)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
しゅん
13
ティンパンアレーの商業性への批判がユダヤ人差別と結びついたこと。ラジオの発展が、ささやくように歌うクルーナーボイスを生み出したこと。「ライヴ(live)」に生の音楽の意味が付随したのは、テクノロジーに対する批判運動からだったおと。商業性と人種性、放送と歌唱技術、言葉の意味と技術進歩。複数のテーマが交差する記述が多く登場することが、本書の面白さだと思う。キーワード集のようなものは、それぞれの相互関連が重要だと思う。 2024/03/14
愛楊
2
非常に良かった。2023年刊行という新しさもあり、ポピュラー音楽研究にいかなるトピックがあるか、どのような文献や言説を用いて理論を組み立てているかを知ることができた。ポピュラー音楽学の教科書としては一番良いのではないだろうか。参考文献や理論紹介も多く、自身で論じるための道具を手に入れることができる。ただ、インターネットのポピュラー音楽としては、「アマチュアリズム」の節が示す通り、未だボーカロイドや歌ってみた・踊ってみた止まりで、音MADやYTPMVに関する成果は未だ無いようだ。2024/02/07
河村祐介
2
この「クリティカル・ワード」シリーズ、簡潔でこれまで買っているシリーズ。で、ある意味で職業的に真打ち登場的な。「ジェンダー、人種、階級、ジャンル、法、アニメetc」などのキーワードで、国内外の現行のポピュラー音楽論の展開、どちらかといえばいわゆる音楽メディア的な批評というよりも、もうすこし学術領域的な掘り下げ方で解説といった感じ。各ターム6ページ程度で簡潔にまとめられているので、日々SNSで繰り広げられているいろいろの理解の下支えとしても重宝というか、もちろん私は仕事のリファレンスとして◎。2023/05/16
なをみん
1
盛り盛り盛り沢山だなあと思って手に取ったけど、やっぱり夏フェス的にあっという間に読み終えてしまった。デジタル時代のポピュラー音楽の現状が薄っすらアップデートできた気もする。「ドストエフスキーはポリフォニー」とか、サブスク時代のジャンルとか、「感情と音楽」とか、「地域とポピュラー音楽のありかたを問うようなミュージアムや常設の展示」とか、ビジュアル系のクィアな解釈とか、気になるワードも盛り沢山だった。2025/07/01
その他
1
他のクリティカルワードシリーズと比較して、歴史の差のせいか少し物足りなさを感じる節が多かったけれど、その分ポピュラー音楽の在り方を現代的に取り上げていたのが良かった。 音楽史的になぞりながら解体していくのではなく、キーワード毎に違う角度からポピュラー音楽を照らしていくような構成は他に読んだことがなかったので、そこの満足度が高い本だった。2023/12/19



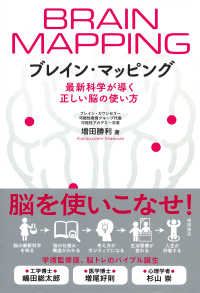
![脳活性スクラッチアート 美しい日本の花と動物 [バラエティ]](../images/goods/ar2/web/imgdata2/40575/4057507590.jpg)




