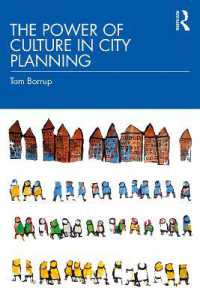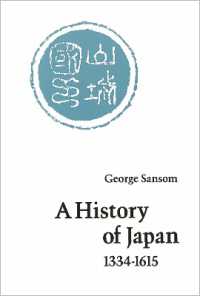出版社内容情報
大量出没と人身事故の増加でマスコミを騒がせるツキノワグマ。背景では何が起こっているのか? 著者が大切にしているのは「自分の眼で見て考える」こと。
クマの棲む山岳から里山まで丹念に調べ歩き、クマと人間との関係を読み解いていきます。「怖い」だけでは終わらせず、クマという生き物を知る面白さを考える一冊です。
内容説明
突然の大量出没ツキノワグマに何が起きてる?「クマは怖い」で終わらせない。自分の足で調べ歩いて、そのむこう側に見えてきたものは…
目次
第1章 秋田県で何が起こっていたのか
第2章 ツキノワグマとの出会い
第3章 ツキノワグマの生活の全体像
第4章 クマ狩りという文化
第5章 再び、秋田県の現場で考える
第6章 人とクマとの関係
第7章 長期的な視点では、何ができるか
著者等紹介
永幡嘉之[ナガハタヨシユキ]
自然写真家・著述家。1973年兵庫県生まれ、信州大学大学院農学研究科修了。山形県を拠点に動植物の調査・撮影を行う。ライフワークは世界のブナの森の動植物を調べることと、里山の歴史を読み解くこと。里山の自然環境や文化を次世代に残すことに、長年取り組む(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
- 評価
稲岡慶郎の本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
AICHAN
36
図書館本。昆虫研究者の著者が、昨年、東北でクマが人里に多数現れるようになって調査を開始した。著者は山形在住で、山形では人里に出てくるクマ(ツキノワグマ)は例年とほとんど変わらないのに、隣県の秋田では急増していた。人里に接近してくるヒグマを北海道の研究者はをアーバンベアと呼んだが、著者はいまひとつ納得できなかった。著者はクマの出そうな場所へ夜のうちに出向き、早朝から監視する。類推できたのは、山の木の実が少ない年は、子グマを連れたメスがオスから退避するため人里に出てくるのではないかということだった。2024/11/03
ようはん
25
ツキノワグマの主食は春はブナの花つぼみでそれ以降はドングリ等の木の実であるものの、それらが凶作になると人里に降りて蕎麦の実や稲を食べる事も。熊による人的被害のリスクが上がったのは山中のエサ不足のみならず狩猟が昔の集団での追い込み猟が無くなり猟銃による遠距離狩猟で人間を脅威と認識出来なくなった事等、人間側の環境の変化も挙げられる。ここ近年の気候変動で凶作のリスクが高くなる、高齢過疎化による狩猟の担い手の減少も考えると熊対策の将来は厳しい状態であろう事を痛感する。2025/09/18
いっしー
14
現地を長年観察した上でのツキノワグマに対する考察。 新たな発見は2つ。1つ目は、越冬前にヒメコマツの樹皮を剥いで出てきた松脂を舐めて便を止め、翌春に有毒のミズバショウやザゼンソウを食べてわざと腹を下し排便すること。その最初の便は乾いてかなり硬いこと。2つ目は、親子グマの母親が駆除され、子グマのみが残ると、子グマは山にいるオスを避けようと人の生活圏を中心に暮らすようになる可能性があること。つまり、有害駆除による捕獲圧が逆に人里に出てくるクマを作り出す可能性があること。実に学びの多い一冊である。 2024/12/11
maya
11
集落にある栗の木にもクマ棚。あの大きな身体で高い木に登るとは。第5章の「再び、秋田県の現場で考える」、第6章「人とクマとの関係」、第7章「長期的な視点では、何ができるか」は、今までの拙い知識が覆る。本書は多くの方に読んで欲しい。2025/07/21
れい
9
【図書館】共生という言葉は美化でしか無いのかとショックを受ける。駆除される個体数も2000頭を超えるとなると、人間に置き換えたら恐ろしくなる。人の都合で殺すことが正しいのかと言い出すと、美化寄りになっていく。できるだけ殺さずにと考えるなら、森林の面積を計画的に管理するべきだとのこと。確かに。駆除されるのは子連れの雌が多く、子どもだけで越冬しようとするから、餌を比較的得やすい人里へ降りてきやすくなる。なるほど。雄が増えると子連れの雌は雄を避けようとして人里に降りやすくなる。政治の力も必要だな。2024/12/11
-
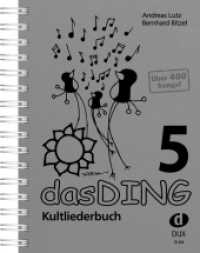
- 洋書
- Das Ding 5