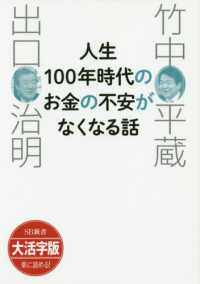出版社内容情報
首都圏をつらぬき、流域に約1000万人が住む荒川は、人の手でつくられた川であることを知っていますか。かつて、荒ぶる川=荒川の流れを変えることで江戸の繁栄はうみだされ、たび重なる洪水から人々を守ってきました。川の歴史と流域の暮らしの変化をていねいに追いかけながら、地球温暖化が原因とされる近年の大規模な水害をどう防ぐかまで、荒川の過去・現在・未来を旅します。
内容説明
水害とたたかい、川の流れを変え、江戸と東京の発展をささえてきた、荒川の過去・現在・未来を旅しよう!
目次
第1章 時代とともに、変化した川・荒川(大きく変化していった荒川の流れ;生活を豊かにするために川の流れを変えた ほか)
第2章 荒川があったから、江戸も農村も発展した!?(日本一広い平野・関東平野の中を流れる;下流になってから東京都に入る ほか)
第3章 東京を水害から守る!―荒川放水路の建設(隅田川ぞいにどんどん工場が建てられる;大水害をきっかけに荒川放水路の建設が決定 ほか)
第4章 今の時代の荒川と、わたしたち(カスリーン台風のとき、もし放水路がなかったら!?;ダム・調節池・放水路でまちを水害から守る! ほか)
第5章 荒川と世界の未来のためにできること(隅田川がきたなくなりすぎて、花火大会が中止になる;わたしたちの生活に、川をふたたび身近な存在にするために ほか)
著者等紹介
長谷川敦[ハセガワアツシ]
1967年広島県生まれ。大学生のときに出版関係の会社でアルバイトを開始し、そのまま就職。26歳のときに「世の中で起きているいろんな問題の原因や解決策を、自分で調べ、考え、書く仕事がしたい」と思い、会社をやめてフリーライター(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
しいたけ
chimako
Aya Murakami
へくとぱすかる
けんとまん1007