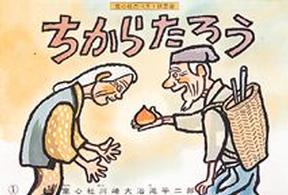内容説明
国内産業の淘汰、雇用リストラの日常化、農業の切り捨て、福祉・教育の市場化、そして新たな「階級」社会が…“構造改革”と“市場原理”で日本はどうなるのか。
目次
第1章 非「市民社会」から「日本型大衆社会」へ(開発独裁型帝国主義下の社会からの移行;戦後政治体制の定着と労使対抗における資本のヘゲモニーの確保 ほか)
第2章 「構造改革」と日本型大衆社会の縮小・再編成(「大衆社会の再収縮」のメカニズム;日本型雇用の転換と企業主義統合の縮小・再編成 ほか)
第3章 大衆社会統合の概念(大衆社会と大衆社会統合の概念;帝国主義と大衆社会統合 ほか)
第4章 政治・文化能力の陶冶と大衆社会(ブハーリン=マルクス型問題構成;グラムシ=「大衆社会」型問題構成)
著者等紹介
後藤道夫[ゴトウミチオ]
都留文科大学文学部教授、社会哲学、現代社会論。1947年生まれ、一橋大学大学院博士課程単位取得。主な編著書に『講座現代日本』(全4巻、大月書店)、『ラディカルに哲学する』(全5巻、大月書店)、『階級と市民の現在』(『モダニズムとポストモダニズム―戦後マルクス主義思想の軌跡』青木書店)、『『帝国主義』と『市民主義』の垣根』(『思想と現代』35号、白石書店)などがある
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
msykst
1
日本型大衆社会=企業統治主義と自民党型福祉(地方再分配と低効率産業保護)のセットであり、福祉国家を軸にする型とはちゃいまっせ、というおなじみの話。ポイントは組合が職種別でなく企業別であり、またQCサークルとか家族ノリがすげぇって事。共通点もあって、どっちもカバーする福祉は二段階あったんだけど、70年代以降の企業の多国籍化に伴ってそれが崩れてさぁどうしようというお話。<帝国>が訳出される前の本なんだけど、日本の特殊性に根ざしているのでこっちの方が読む価値あり。ただ、労働運動の教科書的な色が強くて辟易はする。2009/08/01
ぴろし
0
「補充注文カード」を捨てるにあたり、再読登録。私自身は一度も読んでないけれど。2017/05/07
-

- 和書
- 経済思想にみる貨幣と金融