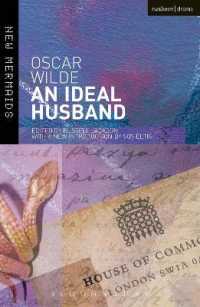内容説明
江戸時代より明治・大正頃において、各種の雛形本は多くの大工にとって必携の設計・施工マニュアルであった。現在では難解ともいえる文言をじっくりと読み解き、これからの大工仕事にも対応できるように図面化したのが本書である。神社建築への基礎が定まり、小さな屋敷神の祠から堂々たる五間社本殿、あるいは拝殿にまで幅広い応用が可能の“必携の書”。
目次
1 鳥居/四足鳥居
2 一間社向造
3 一間社流造
4 二間社
5 三間社
6 五間社
7 拝殿
著者等紹介
富樫新三[トガシシンゾウ]
1929年新潟県に生まれる。1957年山形県立鶴岡工業高等学校建築科卒業後、住宅建設(株)に入社。勤務の傍ら高等職業訓練校(3校)非常勤講師(~1994年)。1958年土地家屋調査士。1962年1級建築士。1974年高等学校教諭2級普通免許取得。1988年山形県産業教育振興功労賞受賞。1989年山形県教育振興功労賞受賞。新・建築設計事務所及び土地家屋調査士事務所創設。1990年職業訓練功労賞受賞。1991年山形技術専門学校非常勤講師(廃校により1993年退職)。現在に至る。主な著書に「日本建築双書 図解規矩術」(理工学社)・「木造建築 屋根工法墨付け図解」(理工学社)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 和書
- 八王子石仏百景