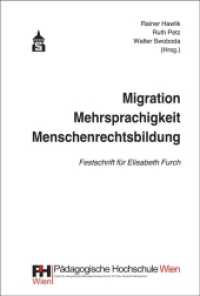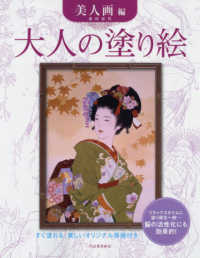内容説明
過酷な紛争地にも、私たちと同じ日常があり、人生がある。違うのは、その日常がある日突然破壊され、多くの人々の「明日」が失われてしまうこと。それでも翌日にはまた、生き残った人々の暮らしが始まる。パレスチナを20年近く取材してきたジャーナリストによる「紛争地で生きる人々」を追った入魂のルポルタージュ。
目次
序章 一九八〇年代、大阪・在日の街
第1章 二〇〇二年冬、パレスチナ
第2章 二〇〇五年冬、メディアに飽きられた戦争
第3章 二〇〇六~二〇〇八年、ユダヤ人の声
第4章 二〇〇七年夏、レバノンのパレスチナ難民
第5章 二〇〇七年、大阪市生野区
第6章 二〇〇八年夏、停戦中のガザ
第7章 二〇〇九年冬、ガザ戦争
第8章 二〇一四年夏、ガザからの電話
終章 二〇一五年、目が覚めたらまた一日が始まる
著者等紹介
藤原亮司[フジワラリョウジ]
ジャーナリスト(ジャパンプレス所属)。1967年、大阪府に生まれる。1998年からパレスチナ問題の取材を続けている。他に、シリア内戦、レバノン、コソボ、アフガニスタン、イラク、ヨルダン、トルコなどにおいて、紛争や難民問題を取材。国内では在日コリアン、東日本大震災や原発被害の取材を行っている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 2件/全2件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
チェアー
13
死人が出ないと国際社会から忘れられてしまうパレスチナ。そこでも人びとは日々生きなければならない。何のために?なんて問いは意味がない。生きているからだ。イスラエルの一般国民も見たくないものは見ず、考えることを放棄する。「イスラエルが無視してるのに、われわれがなんで考えないといけないの?」とばかり、国際社会は無視する。毎日、意図され、意図せざる緩慢な殺人が行われているのに。日本人は他人事?沖縄は?東北は?見たくないものには蓋をして、勝手に「楽しい毎日と未来」を思い描いていないか?2016/08/01
Humbaba
8
援助によって飢えることなく生きることは出来る。しかし、ただ最小限のもののみを与えられて暮らすというのでは、人生に目的を見つけることはできない。将来に対する期待をもてず、ただ生きるだけの生活を続けているうちに、もはや死ぬことだけを考えるようになってしまう。2016/06/24
ア
6
長年、パレスチナ(あと在日コリアンも)を長年取材してきたジャーナリストによる本。イスラエルによる入植や占領の現場、パレスチナの人々の現状、ガザでのUNRWAの実態、日本などによる支援の実質的な効果、レバノンにいるパレスチナ難民など、ニュースを見ているだけではなかなか分からない状況が描写される。とても良い本だったが、パレスチナやイスラエルを日本人としてどう考えればいいのか、余計にわからなくなった。2024/04/21
lily
4
「空の見える監獄」と言われるガザ地区はイスラエル国内でも有数の人口密集地帯。それは自然に生まれたものでなく、ユダヤ人入植・過剰な検問・インティファーダの徹底的抑圧によって人工的に生み出されたものである。在日朝鮮人と暮らす中で国家や個人の在り方を何度も考える環境にあった著者が、一ノ瀬泰造に魅せられてジャーナリストとしてガザ地区に住む人々の声を聴く。中でもガチガチのシオニストとの討論は圧巻。ユダヤ人の「ゲットー・メンタリティ」は今パレスチナ人に向かっている。彼らを囲う壁は、いずれユダヤ人を囲う壁となるだろう。2020/04/30
林克也
3
昔から“なんとなく”興味はあり、しかし、新聞記事や広河さん、E.W.サイード他の本や写真などで得た、ほんの少しの知識しかなかったパレスチナとイスラエル。藤原さんのパレスチナ側からのレポートに、いろいろな面で計り知れない衝撃を受けた。「お前はどうなんだ」、と烈しく責立てられたような気がした。 人が生まれ、生きるとはどういうことなのか。何のためか。俗な言い方だが、生きる目的とは何か。意味はあるのか。まさに生きる屍のように生きていることは、もはや個人の意志ではなく“神”の采配なのか・・・・・・。2016/08/30