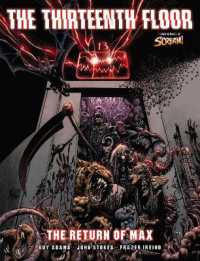内容説明
自分の仕事観や生き方を熟考し、決断した「育休をとる」ということ。育休と向き合った中で何を迷い、何を感じたのか?育休中に生活をどうマネジメントしていたのか?現役教師である著者が、第一子、そして第二子の育休体験をもとに綴る、等身大の記録。
目次
第1章 はじめての育休(ぼくが育休を取得するまで;育休中のぼくの生活;育休から復帰して)
第2章 二度目の育休(娘の保育園入園、そして2人目の誕生;二度目の育休に向けて;二度目の育休生活)
著者等紹介
羽田共一[ハネダキョウイチ]
1983年、兵庫県生まれ。某国立大学大学院修了後、大阪の広告会社に営業職として入社。約2年間の勤務後、小学校教師に転職。公立小学校教師として5年間勤務した後、現在勤務する国立大学附属小学校に転勤。附属小学校での勤務4年目と6年目にそれぞれ約3か月の育児休業を取得。現在、体育を専門の教科として指導している(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
柊子
19
息子は出産直後から3ヶ月の育休取得。奥さんは里帰りせず、生後5日目より夫婦だけで頑張った。大変だっただろう。今更だが、サポートできなくてごめんね。この著者は生後4ヶ月からの育休。それなら首も座っているし、割と楽では?(失礼)。数日間、奥様が入院された事や、コロナ禍での育児などは大変だったと思うが。小学校教諭だからなのか、会話文が教科書表記で、少々違和感。「です。」←となっている。息子の場合も含めて、3ヶ月もの育休を堂々と取得できるのは、まだほんの一部の企業。著者も息子も、恵まれていることに感謝しないとね。2022/09/13
Mana
9
図書館でたまたま手に取ったものだが、なかなか良かった。一時期男性の育休本を読もうとしたが、取得する方法についてばかりで肝心の育休の中身の話がなく育休本を読むこと自体をやめてしまっていた。あくまでn=1の体験で、価値観の合う合わないはあるが、生の声を聞けて良かった。欲を言えば、良かったこと、育休のメリットの他に、妻側への要望もあれば参考になったのにと残念。うちの場合は私が復帰しているから完全に同じではないが、2人育児の大変さは特に共感できた。私も夫に育休をとって良かったと思ってもらえるようにがんばろう!2024/08/09
kitten
8
図書館本。学校の先生(男性)が、三ヶ月育休を取ってみた、という本。著者は先生は育休を取りやすいと書いているけれど、そもそも教員の仕事が大変過ぎて平時に育児に割ける時間が少ないことが問題だと思う。育休を取るメリットは、「主婦の偉大さ」を思い知ることじゃないだろうか。私は育休とってないけど、育児にはがっつり関わってたよ。家事はからきしやったけど。がっつり育休を取ることで、父親としての自覚ができて、人生が豊かになるのはよいこと。2021/11/20
鳩羽
5
小学校の先生をしている筆者が、第一子、第二子とそれぞれ三ヶ月の育休を取った経緯や過ごし方、妻との家事育児分担などを事細かに記した本。妻が育休を取っているのになぜ夫もとるのか、の、休む側からのメリットが素直に語られている。そもそも必要な時に十分休めたり、定時で帰れたり、保育サービスがあるのであれば、育休を充実させる必要はないと思うが、制度の中で、ある時間を上手く使った例として、男性には受け入れやすいのではないかと思う。取りたい人が取れるのが大事であって、いろいろ?と思うことがあっても受け入れる方が良い社会。2021/09/26
しゅんぺい(笑)
4
育休をとるまでの経緯とか、とってからのあれこれとかを書くのに300ページ費やすって、なんかかっこいいな。それだけで家族思いなひとなんやろうなあ。この著者さんたちみたいに、夫婦一緒に子育てできればいいし、おたがいに対するリスペクトがあればいい。2022/01/10
-
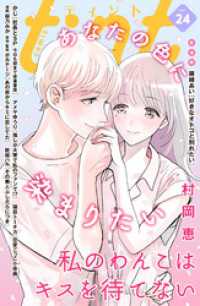
- 電子書籍
- comic tint vol.24
-
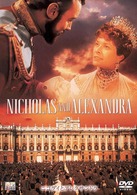
- DVD
- ニコライとアレクサンドラ