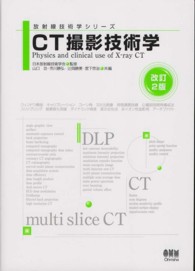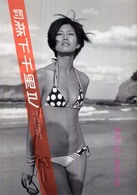内容説明
元禄時代の歌舞伎役者は演技と科白ばかりでなく、芝居の中で唄を歌うことがあった。唄の巧拙も役者の評価基準の一つであった。享保中期以降になると、役者・音曲方は分化・専業化し、座付き演奏者の専門芸となり、役者は全く唄を唄わなくなり、現在見る歌舞伎の様式が成立する。本書は8000点におよぶ小唄・長唄正本(薄物正本)の調査により初めてその実態を明かにした。
目次
第1部 長唄正本の版行形態(中村座(享保期から寛政三年)
市村座(享保期から寛政期)
森田座・河原崎座(享保から享和期))
第2部 長唄成立史(正本の刊行と長唄の形成;小歌から長唄への展開)
第3部 中村座における株板化の動向(地本としての長唄の薄物;正本と偽版;相版化;版元の交代;「後版」グループ;株板化の要因;天保期の芝居町移転後)
付編(江戸歌舞伎における長唄の形成―芸態の変化を捉えて;河東節正本の版行に関する一考察―江戸歌舞伎における初期の音曲正本と位置付けて)
著者等紹介
漆〓まり[ウルシザキマリ]
1958年生まれ。武蔵野音楽大学ピアノ科卒。東京芸術大学楽理科卒。同大学院博士課程修了後、同大学助手、東海大学非常勤講師を経て、国際日本文化研究センター研究部機関研究員。2017年6月没
原道生[ハラミチオ]
明治大学名誉教授。日本近世文学。『近松浄瑠璃の作劇法』(八木書店、2013。角川源義賞)など(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 電子書籍
- ウルトラ兄弟物語4巻 マンガの金字塔