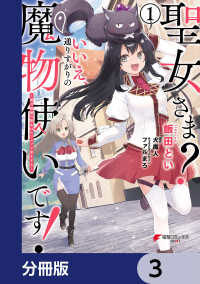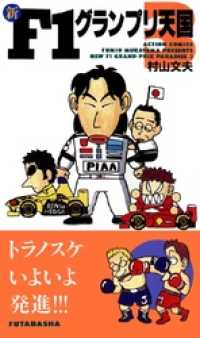出版社内容情報
「シカクいアタマをマルくする」でおなじみの進学塾・日能研のトップが、本当の学力を子どもが身につけるための方法をお伝えします。
今から16年後、2030年には、3人に2人が「今はまだ存在していない職業につく」と言われています。そんな現代を子ども達が主体的に生き抜くためには、どうしたらよいのでしょう。「シカクいアタマをマルくする」でおなじみの進学塾・日能研の代表を務める著者が、世の中の常識になっている「学習習慣」の幻想から抜け出し、子ども達が自ら学べるようになためにはどうしたらよいか、メッセージを送ります。
【こんな読者の方におススメします】
・「学習習慣」をつけることが子どもにはいちばん大事、と考えている。
・クラスの友だちと勉強で競争するのは当たり前、と考えている。
・「困る」よりも「困らない」のほうが良いと、考えている。
・なにはともあれ机の前にじっと座っていることは大事、と考えている。
・わが子には、未来に向かって新しい道を切り拓いてほしい、と考えている。
はじめに ― 「学び」の現場で起きていること
第1章 教わり家から学び家か へ
1.「学び家」ってどんな人?
2.「学び家」だからといって、すべて自分でやる必要はない
3.大切なのは「私が意見を持つ」こと
4.小学生のうちに「しっかり困る」経験をする
5.日能研が板書主義をやめた理由
6.教科書もマニュアルもない世界で起きること
第2章 不安定という自由を子ども達に手渡そう
1.「立ち歩き」だけで、学級崩壊?
2.何でも右へ倣え! ~決めるのが不得意な日本人
3.「安定」という枠に縛られない生き方
4.あえてテストの正解を受け取らない子ども達もいる
5.終わりをつくらず、変化し続けること
第3章 縦につながる学び、横に広がる学び
1.学びの縦関係、横関係とは?
2.公立学校は典型的な縦関係でできている
3.「学び家」が仲間を持つ意味
4.ラーニング・コモンズというスタイル
5.ラーニング・コモンズをめぐる「オンとオフ」の話
第4章 新しい組み合わせが生み出すもの
1.カツオの刺身にマヨネーズという発想
2.物事は一度疑ってみる
3.「なんで?」が大切
4.同じ材料の新しい組み合わせを考える
5.「学び家」と再構造化について
6 知って、手放すこと
第5章 子どもを「学習習慣病」から守る方法
1.「オタク道」に学ぶ賢い手放し方
2.習慣化された行動と意識的な行動
3.個性と学習習慣は“同居”できない
4.わが子を「学び家」にする方法
おわりに― 「学び家」が切り拓く未来
【著者紹介】
1954年、横浜市生まれ。小学生のための学習塾「日能研」代表。子どもの進学後の成長を考え、「課題を見つけ、解決する力」を伸ばす学びを目指す。2005年より「親業訓練協会」会長として親と子、教師と生徒等の人間関係を作るコミュニュケーション方法の普及に力を入れる。またNPO法人「体験学習研究会」を通じて学校における「体験学習」の効果的な活用への働きかけに努めている。
目次
第1章 教わり家から学び家へ(「学び家」ってどんな人?;「学び家」だからといって、すべて自分でやる必要はない ほか)
第2章 不安定という自由を子ども達に手渡そう(「立ち歩き」だけで、学級崩壊?;何でも右へ倣え!~決めるのが不得意な日本人 ほか)
第3章 縦につながる学び、横に広がる学び(学びの縦関係、横関係とは?;公立学校は典型的な縦関係でできている ほか)
第4章 新しい組み合わせが生み出すもの(カツオの刺身にマヨネーズという発想;物事は一度疑ってみる ほか)
第5章 子どもを「学習習慣病」から守る方法(「オタク道」に学ぶ賢い手放し方;習慣化された行動と意識的な行動 ほか)
著者等紹介
高木幹夫[タカギミキオ]
1954年横浜市生まれ。小学生のための学習塾「日能研」代表。2005年より「親業訓練協会」会長。NPO法人体験学習研究会理事、学校法人明星学苑評議員、公益財団法人日本アウトワード・バウンド協会理事、公益社団法人ガールスカウト日本連盟評議員、GEMS運営委員、PAJ(Project Adventure Japan)エグゼクティブディレクター、一般社団法人RQ災害教育センター理事、NPO法人日本エコツーリズムセンター理事、NPO法人日本バイオダイナミック協会理事、ジュニア防災検定評議員、神奈川県警察官友の会副会長、港北警察官友の会会長、UCLAファウンデーション理事、日本エキスパートセキュリティ代表取締役(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
motoryou
motoryou
epitaph3
motoryou
motoryou