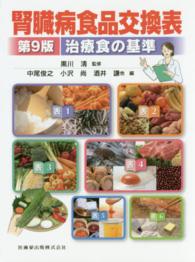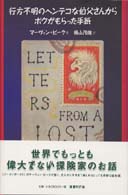内容説明
上から目線、揚げ足とり、バッシング―。さまざまな「言葉」が氾濫するソーシャルメディア時代、人と人が本当につながるために必要な大人の知的作法とは?―。
目次
物語の獲得
街と物語
親供養
揚げ足をとる人々
国を祝福しよう
かっこいい老い方
知性は贅肉のようについてくる
中立ぶるのはもうやめよう
なぜ人は人を叩くのか
定型圧力のすさまじさ
執着をとる方法
愛の反対語は敬意
著者等紹介
内田樹[ウチダタツル]
1950年東京都生まれ。思想家。神戸女学院大学名誉教授。凱風館館長。専門はフランス現代思想、映画論、武道論。2007年『私家版・ユダヤ文化論』(文春新書)で第6回小林秀雄賞を、10年『日本辺境論』(新潮新書)で新書大賞2010を受賞
名越康文[ナコシヤスフミ]
1960年奈良県生まれ。精神科医。専門は思春期精神医学、精神療法。臨床に携わる一方で、テレビ・コメンテーター、雑誌連載、映画評論、漫画分析などさまざまなメディアで幅広く活躍中
橋口いくよ[ハシグチイクヨ]
1974年鹿児島県生まれ。作家(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
けんとまん1007
31
やっぱりそう感じているんだなと納得。揚げ足を取る。この一言に尽きる。言葉尻を無理やり捉えて、そこだけを自分勝手な屁理屈で攻撃する。コジンレベルでもそう感じることが多いし、メデイアでもそう思う。1対多となって、集中砲火。自分と近いもの、あるいは自分のほうから、それに合わせて安心するということだと思う。聴く前に喋るというが増えているからだと思う。話すではなく喋る。名越先生、内田先生、さすがです。2015/03/02
p.p.
20
あっという間に読み終わってしまった.まさに「うどん的文章」.「物語」というキーアイテムは内田氏の著書では繰り返し登場してくるが,それを読む度にこれを忘れて無味乾燥な人生を歩んでしまっていることに気づかされる.「言葉は本来,攻撃的である」という言明は,自分にとっては目から鱗だったが,普段あまりにもなげやりに言葉を使ってきて,それで人を傷つけてたんだと納得.他者の自己同一は実に厄介な病気で,それを祓う道具が「敬意」だというのは,心に留めておく.とりあえず飲み込んだはいいけど,消化するのは時間がかかりそう.2014/01/14
Gatsby
20
この前の対談集『原発と祈り』において、私は橋口いくよという人を初めて知った。なんかとても不思議な感じがする人なのだが、内田樹と名越康文の二人と堂々とわたりあっている様子に感心した。この本においても、ますますその存在感が増している。内田・名越コンビに橋口が加わることで、彼女はよき触媒として機能している。キーになる言葉は、やはり二人から出されるのだが、それを引き出し、またテーマとして深化させるのが橋口の力である。ネットで調べれば、どんな人なのかすぐにわかるのだが、しばらくこのシリーズでだけ、会うことにする。2013/03/11
金城 雅大(きんじょう まさひろ)
19
内田樹9冊目。 内田樹、名越康文、橋口いくよによるダ・ヴィンチ連載対談の書籍化。 橋口いくよだけ知らなかった。美人さんだなぁ。 内田樹は「畏兄」と冠され、提示されたトピックや問題に対してソリューション的意見を述べるアドバイザーという立ち位置で切り込んでいる。その分、普段の著書と趣が異なり、なんというか、内田節が薄まってマイルドな感じだ。 「第7章 知性は贅肉のようについてくる」と「第12章 愛の反対語は敬意」が良かった。2018/09/02
れんこ
16
ダヴィンチで連載されていたもの。意味が分からなくてもひとまず飲み込みことに意味があるetc.メモを取りながら。2017/06/24
-

- 和書
- 現代公衆衛生学