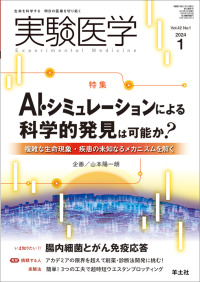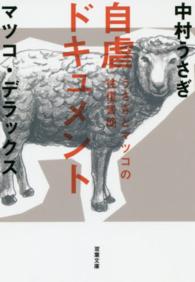内容説明
「赤ちゃんを抱いて入る」「手錠でつながれる」など革新的なお化け屋敷をつくり続けてきたヒットメーカーが“恐怖の法則”を初めて解き明かす。幽霊なんていないと思っているのに、怪談を聞くとトイレに行けなくなるのはなぜか?風呂場の髪の毛が気持ち悪いのはどうしてだろうか?―実践に基づいた“恐怖論”ここに誕生。
目次
第1章 人を驚かせる仕事
第2章 お化け屋敷のつくり方
第3章 お化け屋敷の心理学
第4章 恐怖を操るテクニック
第5章 恐怖の正体
第6章 恐怖の効用
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
6(ロク)
4
屈指のお化け屋敷プロデューサーが「恐怖」と言うアトラクションを組み立てる方程式を論理的に解説してくれ、なかなか腹落ちさせてくれる良本。長年深い興味があった「グロテスク」に対する解釈と「恐怖と笑い」の関係性考察が個人的見解と一致して新年早々爽快で御座います。まあ何はともかく表紙が日野日出志ってだけでも好事家は「買い!」の一冊かと。怖がらせるだけでは駄目ってところが深いよねぇ。2015/01/06
Prussian_Blue
3
最後少し説教臭がありましたが恐怖を生成するテクニカルな部分は非常に面白かった。ただ怖いだけでなく恐怖を通じて楽しさを与えることが良いお化け屋敷の条件であると。なるほど。2018/02/11
紅独歩
2
「恐怖」をテーマにした本は多々あるが、「お化け屋敷のプロデューサー」という怖がらせる側からの視点が斬新。専門的な心理学や脳生理学に踏み込む事は無いが、豊富な実績による分析は非常に説得力がある。怖がらせる事を「接客」ととらえ、できるだけ多くの人を満足させたいという著者の姿勢が素晴らしい。2009/06/14
トーテムポールさん
1
お化け屋敷を作り続けてきた、という現場(?)の立場から、恐怖の起こるメカニズムと、そのこだわりを解説。緊張と弛緩。客の想像力を暴走させる。恐怖を意図的に伝染させる、など。お化け屋敷を「恐怖を楽しむ機会」と捉え、「恐怖を克服する」肝試しと差別化を図ろうとしているところに、根本的な、お化け屋敷哲学がある感じ。2019/06/24
katta
1
お化け屋敷のプロデューサーというと、ちょっと如何わしい感じがするが、アミューズメント施設としてはかなり難しそう。経験に基づいて進化していくお化け屋敷には人の隠された心理が上手く反映されていた。2009/06/22
-

- 電子書籍
- あらがえ!ダークエルフちゃん【単話版】…
-

- 電子書籍
- 赤い糸に気をつけてください【タテヨミ】…