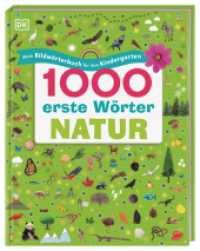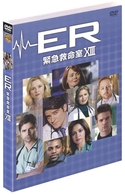出版社内容情報
近年の将棋AIは振り飛車をまったく評価しません。それはなぜなのか。「現代将棋を読み解く7つの理論」の著者、あらきっぺ氏が論理的かつ明快に解説します。
しかし、もう振り飛車をやめるべきなのかといえばそうではありません。
振り飛車は、人間の認知能力にとってはアドバンテージが多く、むしろ有利に立ち回れることもあるのです。
AI時代でも、勝負は人間のもの。振り飛車を指す人も指される人も、必携の一冊です。
内容説明
振り飛車に未来はあるか?理論的には欠陥が多い、それでも実践的には有力な戦法と言える理由。
目次
序章 対抗形のルール
第1章 初速の違い
第2章 急戦の脅威
第3章 穴熊の価値
第4章 角交換の是非
第5章 飛・角・桂の機動力
第6章 桂・香の安全度
第7章 位置エネルギー
第8章 後出しと多様化
第9章 両立と相対化
終章 振り飛車の未来
著者等紹介
あらきっぺ[アラキッペ]
本名:荒木隆。平成16年6級で森信雄七段門。平成28年三段で退会。奨励会退会後もアマチュアとして将棋の活動を続け、第42回朝日アマチュア将棋名人戦全国大会にて4位の成績を収める。並びに招待選手として出場した第13回朝日杯将棋オープン戦において、出口若武四段、大石直嗣七段を破る快進撃を見せた(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Sam
40
何とも魅力的な書名ではないか。つい釣られて買ってしまったよ。そして読んでみてその面白さに目を見張らされた。「初速の違い」、「エリアR」、「位置エネルギー」、「後出しと多様化」等々、将棋の解説本(そんなに読んでないけど)ではまずお目にかからない斬新なコンセプトの数々。加えてどれも非常に説得力のある解説で思わず唸った。そして結論。大山康晴を引き合いに出しながら、居飛車は理論を、振り飛車は勝負を重視する戦法であるという。納得。なんだか一冊通して見事なお手並みで感心してしまった。他の著作もぜひ読んでみたい。2024/08/17
ま
30
振り飛車の欠点についてここまで真正面から論じた本がかつてあっただろうか。振り飛車党の自分は何度も目を背けたくなった。そして、そんなにカタルシス要素もなかった。どうすればいいんだ。ミレニアムは組んでみようかな。コラムの出来は相変わらずでした。2024/06/07
akihiko810/アカウント移行中
21
「振り飛車は不利である」という理由を詳しく説明した本。印象度B 信頼のおけるあらきっぺ本。なのだが、今回は強くなるための考え方ではなく、「なぜ振り飛車は不利なのか」という考察と証明。居飛車の「穴熊と急戦の両天秤」に、振り飛車は完全には対応しきれない、という話。ならば振り飛車を指す理由などないではないか、なのだが、「振り飛車は、長期戦になりやすいので逆転の確率が上がる戦法」というまとめ。私が振り飛車やる理由も「相居飛車は玉が薄くていや」だから、まあ、そういうことなのである2024/07/05
hiroy
7
将棋の理コトワリを明確に言語化して見える化してくれる氏の手法はいつもながら見事というほかないが結構面倒くさいのである。今回は振飛車の弱点をこれでもかと言わんばかりにあげつらってくれている。初速が遅いから急戦持久戦と対応されやすい、左側の桂香を取られやすい、そもそも飛車の位置エネルギーが段違い等、わかっとるわ!という事を改めて叩き込まれる。でも振飛車相手に負けるしなあ、居飛車は覚えるの大変だし四間なんかほぼ一直線でラクだぞw 低級低段アマチュアなら振飛車継続で全然イイでしょと氏も言外に言ってくれてる。違う?2024/02/12
toshiyuki83
2
将棋高段者を対象としたこの一冊は、現代振り飛車の課題と可能性について論じています。振り飛車党として序盤理論に強い関心を持つ私には目新しい発見はありませんでしたが、著者の言語化能力と盤面説明力は卓越しており、複雑な将棋理論が分かりやすく解説されています。ただ、本書の大半が振り飛車の欠点分析に費やされ、読者が期待する「希望」の部分が極めて少ない点は残念です。「実戦的に強い」という主張も具体例が乏しく、著者独自の視点でより掘り下げてほしかったと感じます。2024/12/17
-

- 電子書籍
- やさしく学べる線形代数
-
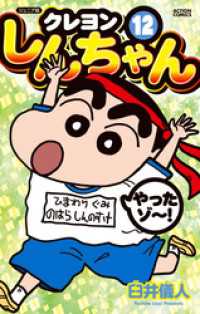
- 電子書籍
- ジュニア版 クレヨンしんちゃん 12 …