内容説明
最新の序盤手順を解説した本は多くありますが、本書は「なぜ現在その形が流行しているか」を戦法の歴史からさかのぼって解説した画期的な一冊です。将棋を指す方はもちろん、自分ではあまり指さないという方でも十分理解できるように、図面に矢印等の記号をふんだんに使い、直感的にも分かりやすくなっています。本書は基本用語の解説からプロ将棋の最新局面の解説にまで至ります。自分で指す上でもプロの将棋を観戦する上でも、大いに役立つ内容です。
目次
第1部 序盤の基礎知識(相居飛車初めて講座;相居飛車の各基本図までの手順)
第2部 相居飛車の歴史を振り返る(相居飛車の歴史;相居飛車を理解するためのキーワード)
第3部 相居飛車、主流戦法の紹介(矢倉―これぞ将棋の純文学;角換わり―攻め切るか受け切るか、白熱の攻防;一手損角換わり―手損の意味を根本から揺さぶる新作戦;相掛かり―2六飛型と引き飛車、二つの顔を併せ持つ;横歩き取り―食わず嫌いは無用!最もスリリングな戦型)
著者等紹介
上野裕和[ウエノヒロカズ]
1977年4月13日生まれ。神奈川県厚木市出身。1991年6級で安恵照剛八段門。2000年10月1日四段。2007年4月1日五段。序盤の研究、分類で有名。また、若くして日本将棋連盟の理事職を経験するなど、多方面に渡って活動している(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
かわうそ
20
序盤をおさらい。角換わりと横歩取りをメインにしたかったけど、現実としてなかなか採用機会が少ないことを悟った。そんなわけで矢倉を中心に再読。26歩型の桂馬の活用や雀刺しなどはとても参考になる。それにしても、終盤なら10数手以上の詰みも見えることがあるのに、序盤の同手数が見えないのはなぜなんだろうか…単純に選択肢が多いから?局面に対する経験が少ないから?何にせよもう少し序盤を指せるようにならないと、昇級どころか中盤もままならない。せっかちな性格もあるだろうけど、序盤は時間をかけて丁寧にするべきなんだろうな。2015/10/26
かわうそ
18
24で昇級降級を繰り返し、何とか強くなりたいなーと思っていたら、はしぞう様より天の声を頂き本書を勧められた。いろいろとできたらいいんだろうけれど、ちゃんと絞って『角換わり』と『横歩取り』を勉強してみることに決定。あとは定跡をしっかりと覚えて時間をかけてじっくり手を読んで、実戦で繰り返し練習するべし。『腰掛け銀』がちょっと難しそうだけど、毎回やってたらそのうちにわかってくるだろうか?24で勝てるようになったら、街の道場にも行って試してみようと思う。目標ができるとなんだか頭がスッキリしてきた。がんばるぞー☆2015/10/05
マッサー
12
戦法の歴史が書かれていて、棋士達の研究の成果、また、それを攻略する研究の繰り返し、の将棋の魅力に触れることができた。❗️❗️❗️❗️❕2021/03/07
無識者
11
将棋の棋力を上げるというよりかは、プロで実際に刺される相イビシャを級位者にもその対局の面白味が伝わるように解説されている本です。中原、加藤、米長の3強時代から、つい数年前までの将棋の発達を凝縮して書かれています。プロの一手一手の深さ、というものに感動します。読了したときの感想としてメチャ将棋を指したいです。2017/01/31
ヨッフム
10
角換わりで無理筋とされている、先手の棒銀と早繰り銀が、一手損角換わりでは、主流戦法になってしまう不思議さ。腰掛け銀と併せて、まるでジャンケンのような絶妙なバランスが面白く、将棋というのは本当に良く出来たゲームだと思います。自分は振り飛車党なので、先手後手を強く意識することはないんですが、相居飛車戦では、まさに死活問題。守勢になりやすい後手側が、いかに先手の攻めを凌いできたか、先人達が作り上げてきた定跡の歴史を一から説明し、なおかつ現在の最新型も紹介してくれる、とても級位者フレンドリーな構成になってます。2015/03/02
-
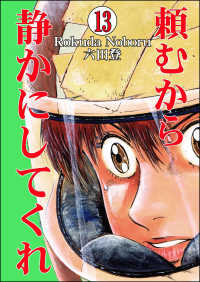
- 電子書籍
- 頼むから静かにしてくれ(分冊版) 【第…
-
- 洋書
- The Wackness








