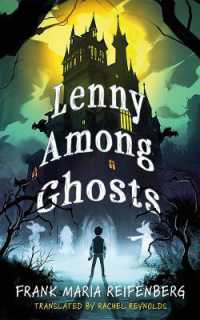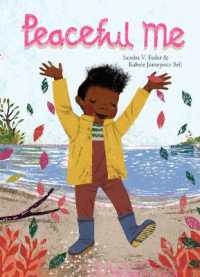出版社内容情報
1969年から10年間流刑地ブル島に勾留され、表現手段を奪われたプラムディヤが、独房の政治犯に日夜語って聞かせたという途方もないスケールの4部作の第3部です。
訳者より:鋭い眼光。短く刈り上げた頭。太い二の腕。節くれだった指。その指からブラインドタッチの猛烈なスピードで紡ぎ出される物語。それは書斎の中で苦悶する作家というより、茶褐色の上半身に汗を光らせながら坂道を駆け上がるベチャ引きに似ている。現代東南アジアを代表するプラムディヤ・アナンタ・トゥール(1925年生れ)の畢生の大作
『人間の大地』シリーズの第3部にあたるのが『足跡』である。前2作『人間の大地』『すべての民族の子』が、主人公であるジャワ貴族ミンケ青年の成長の物語であったのに対し、この巻では1901年から1912年のバタヴィア(現ジャカルタ)、バンドゥン、バイテンゾルフ(ボゴール)を主舞台として、バタヴィア医学校に入学したミンケがインドネシアの民族主義運動に身を投じ、新しい時代を切り開いていく苦難の闘いが描かれる。
内容説明
プラムディヤ・アナンタ・トゥールは現代インドネシアが生んだ最高の作家であり、彼の文章は熟成しつつある現代インドネシア語の頂点に立つといわれる。戦争と革命の「45年世代」の象徴的存在として、独立革命から今日まで、激変するインドネシアの真っただ中に身を置きつつ、時代の波に翻弄されながらも逞しく生きる人びとの哀しみと歓びを重厚な筆で綴った彼の物語は、そのまま歴史の証言であり、読むものの心を激しく揺さぶる。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
syaori
38
許亜歳の手紙が縁で知り合った安山梅の言葉とその活動を目の当たりにしてミンケもようやく現地民の組織と新聞を立ち上げることに! しかしその活動が実を結び活動が大きくなるほど新たな問題や葛藤が生まれます。様々な民族が混在する東インドを団結させるものは? 宗教か商業か、もっと別のものなのか。様々な対立から組織は分裂し、終息し、また別の組織が立ち上がる。そのなかでも人々は次々と目覚め立ち上がり、そのエネルギーは植民地政府の計画を断念させるほど。もうこの流れは止められない、と思ったところに政府の非常大権発動で4部へ。2017/12/04
Keusuke Sakai
4
帯の「インドネシア最高の文学」っていうのは決して大げさではないでしょう。ブル島4部作の3作目、5冊目にして、国民国家形成に目覚めた主人公に最大のピンチが。多少の?を帳消しながら、アドレナリン全開で700Pがあっという間に過ぎていきます。インドネシアの他民族性を理解する上でも最高の一冊。2016/08/06
belier
4
ブル島4部作の3作目。舞台も雰囲気もガラッと変る。主人公は大物に成長し当時の実在の人物が多く登場する。非常にダイナミックでめくるめく展開。正直、自分の好きなタイプの小説とは大きく離れてしまった。作者の思考やアイデアが噴出しすぎで登場人物が生きていない感じ。ただ、インドネシア民族主義の母とされるカルティニがジュパラの娘として登場し、主人公たちと議論したのは興味深かった。死後もその時の会話を主人公が反芻する形でなんどか語られる。この偉大な作家アナンタトゥールのカルティニへの敬愛と共に批判も見れてよかった。2015/12/20
たなしん
4
とうとうここまで来たか、と思う。インドネシアの大河ドラマでありジェットコースターのようなエンターテイメントであり呆れるほどの真っ当なパワーで独立の一つの場面を切り取ったこの作品は、新聞という手段によって団結していく現地の原住民達の、政府に張り巡らされた策略との戦いによって786ページをカタルシスの渦で覆い尽くす。リアリティという点では不自然な点も多すぎるけど、口述筆記の勢いがそれを強引に押しやってしまって結局有無を言わせません。悲劇はクライマックスで断線され、最終作『ガラスの家』に続くようです。凄かった…2012/03/21
みづはし
3
物凄いエネルギーが伝わってくる本。オランダの植民地支配にジャーナリズムでの対抗を試みた実在の人物ティルト・アディ・スルヨをモデルにした歴史小説。単純にオランダを悪としているのではなく、インドネシアの発展にはオランダ式の教育が必要であることも議論されている。インドネシアは民族として団結すべきなのか宗教で団結すべきなのか、当時のインドネシアの 民の葛藤がこれでもかというほど伝わってくる密度の濃い本。2015/09/21