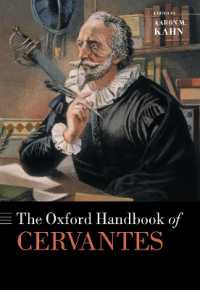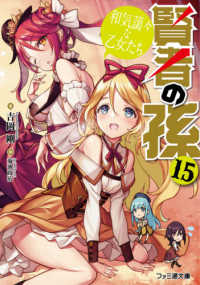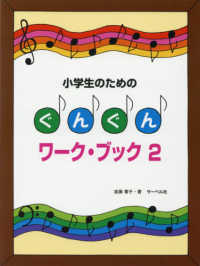内容説明
約27年にわたり劇団四季に在籍し、退団後も浅利慶太と劇団四季を見つめ続けてきた著者が、追悼の念を込めて上梓。劇団創立、華麗にして重厚なる人脈、転機となる数々の作品、四季節「母音法」…etc.。欠くことができないキーワードに導かれ、人間・浅利慶太に迫る始まりの一冊。
目次
わが心高原に―加藤道夫との出会い
劇団四季創立と加藤道夫の死
演劇の回復のために―新劇を創った人々へ
天才金森馨との邂逅
日生劇場と華麗にして重厚なる人脈
日生劇場の始動と試練
決断の時
『なよたけ』への想い
「母音法」―四季節の完成
『キャッツ』―夭逝せる同志への慰謝
ミラノ・スカラ座の熱狂―オペラ『蝶々夫人』演出
「第二国立劇場(仮称)」建設の功労者として
『ミュージカル李香蘭』―真実を見つめて
著者等紹介
梅津齊[ウメツヒトシ]
1936年北海道稚内市生まれ。樺太泊居町にて終戦。北海道学芸大学卒。熊本大学大学院日本文学研究科修士課程修了。1962年、劇団四季入団、演出部。浅利慶太氏に師事。1970~1989年北海道四季責任者として劇団四季公演及び『越路吹雪リサイタル』北海道公演を担当。1985年、札幌市教委、札幌市教育文化財団の共同事業として、演劇研究所「教文演劇セミナー」(夜間二年制)を設立、指導。2005~2010年、熊本学園大学非常勤講師。1994年以降、熊本壺渓塾学園非常勤講師(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。