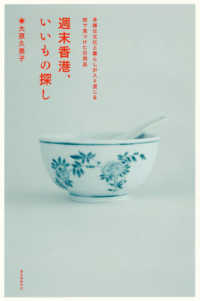内容説明
震災での日本人の団結力は、神道の文化に根ざしているかもしれない。「理屈より気持ちが大切。人にやさしく、明るい」神道の本質を理解しよう。
目次
1 神道の特徴(所属意識が希薄;創始者がいない ほか)
2 神道の基本概念(言挙げしない;穢れを嫌う ほか)
3 神社という不思議空間(神社の成り立ち;鳥居は神社のシンボル ほか)
4 神道の歴史(原始神道の時代;農耕儀礼との関係 ほか)
著者等紹介
井上順孝[イノウエノブタカ]
1948年鹿児島県生まれ。東京大学文学部を卒業、同大学大学院人文科学研究科博士課程中退。東京大学助手、国学院大学講師などを務めるかたわら、近代の宗教運動の比較研究などに携わり、博士号を取得。専門は宗教社会学。現在は国学院大学神道文化学部教授ならびに同大学日本文化研究所所長を務める(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
うえ
6
「神道では動物を神の使者とみなす…これを神使といいます。特定の動物が神意を伝えたり、吉凶を示したりすることがあると考えるわけです。…神社の中には神使・眷属が狛犬になっているところがあります。例えば、大豊神社では祭神である大国主神を火の中から救ったといわれる鼠を“狛鼠“として、社殿の前に置いています。また、護王神社では祭神である和気清麻呂が宇佐神宮に行く途中で足を痛めたところ、三百頭もの猪が現れて清麻呂を守り、足の痛みも治ったという伝説に基づき、狛犬ならぬ“狛猪“が境内に置かれています。」2025/09/18
ybhkr
0
読んでいてふいに、母の兄が霊璽簿に載っていたのを調べたかったんだ、ずっと前から!と思い出し、検索しながら呼んだので45分では終わらなかった。14歳からの、ということですが、世間一般の14歳ってこれ読んで45分で理解できるの?すごいな!わたし、ところどころ検索しながら読んでしまったよ…。眷属とか遷都とかディティールについては専門書を読んだり、新新宗教についても調べたりしたけど、根本ではよくわかってないことが沢山あった。ヲタクだから神話は嗜んでいるけども、後半なかなか勉強になった。七草粥、海開きは神道の儀式。2016/11/18
oDaDa
0
日本人が日本人たるために、神道を抜きにしては語れない。神道こそ日本人の宗教であると声高に言いたい。なんでもかんでも受容し、新たなものに吸収してしまう日本人の特性は、神道の寛容さから通じているのではないだろうか。それにしても、日本人は自国の宗教事情を知らなすぎる。それはある種、何事も強制しない神道の特性でもあるのだろうが。例えば、「勤労感謝の日」という休日は、神道の例祭である新嘗祭(収穫の感謝をする祭)が起源であることを、日本人のどれだけが知っているのだろうか。それを勤労感謝の日にしてしまうあたり、やはり日2013/07/08
あり
0
宗教に関して無学な自分にとって、とっかかりとしてとても良かったと思います。深すぎず、それでいて日常の些細な疑問が解けたり「もっと知りたい!」と思える本ではないかと。もう少し勉強したいと思います。2012/10/18
akiu
0
色々なエピソードがありつつ、簡潔にまとまっていてさっくり読めました。歴史の部分だけはちょっと難しく、45分では読み終わりませんでしたが、とっかかりとしては良かったと思います。2012/04/08
-

- 電子書籍
- 欠けたる月の満が如し ―あなたの手を取…
-

- 電子書籍
- 平民の私ですが公爵令嬢様をたぶらかして…