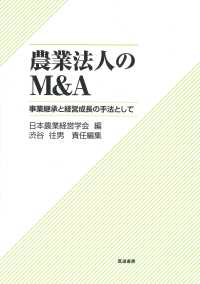内容説明
舞台の裏ってどうなっているの?衣裳や装束はどうやって着けるの?鬘は?小道具は?大道具は?豪華な監修陣を迎え、普段は知ることのできない舞台裏を貴重な写真で紹介します。
目次
第1幕 歌舞伎(歌舞伎の魅力;歌舞伎の歴史;歌舞伎鑑賞の楽しみ 歌舞伎十八番 ほか)
第2膜 文楽(文楽の魅力;文楽の歴史;文楽鑑賞の楽しみ近松門左衛門 ほか)
第3幕 能と狂言(能と狂言の魅力;能と狂言の歴史;能楽鑑賞の楽しみ世阿弥の精神 ほか)
著者等紹介
山田庄一[ヤマダショウイチ]
大正14年大阪生まれ。京都大学医学部薬学科卒業。岐阜薬科大学助教授、毎日新聞記者を経て国立劇場勤務。劇場芸能演出室長、同副部長、調査養成部長を歴任し、昭和57年より国立劇場理事を務める。任期満了後、国立能楽堂主幹を務め、平成3年に定年退職。以後、歌舞伎・文楽の演出を多数手掛け、古典の復活上演や新作のための台本制作にも意欲的に取り組む
吉田簑助[ヨシダミノスケ]
本名、平尾勝義。昭和8年8月8日大阪生まれ。15年6月、三世吉田文五郎に入門。17年3月、桐竹紋二郎と名のり翌年6月「絵本太功記」三法師丸で初役。23年8月、桐竹紋十郎の門下となる。36年6月三代吉田簑助を襲名。平成6年5月、重要無形文化財保持者(人間国宝)に認定される。現代文楽を代表する立女形。吉田玉男らとともに現代の文楽人形遣いを牽引している。平成10年大病を患うも、芸に対する熱い情熱で翌年みごと復帰を果たし、現在も舞台上で多くの観客を魅了し続けている
大藏彌太郎[オオクラヤタロウ]
能楽師大藏流狂言方。本名、大藏基嗣。昭和23年3月15日、第二十四世宗家大藏彌右衛門の長男として生まれる。父に師事。53年10月「唐相撲」の唐子で初舞台。72年9月「釣狐」を初演。平成元年大藏宗家の成人名である大藏彌太郎を襲名。平成17年3月第二十五世として宗家を継承する。父の型に忠実で堅固な芸風を受け継ぐ。アメリカ・ヨーロッパ・アジア・中東と海外公演も多い。舞台活動の一方で、東京・千葉・名古屋・伊勢・奈良・兵庫等各地の稽古場で狂言の指導・普及に努める。日本能楽会・能楽協会会員
岩田アキラ[イワタアキラ]
昭和23年神奈川県生まれ。松竹写真部を経て現在、国立劇場、国立能楽堂嘱託写真家。芝居とそこに携わる人々をこよなく愛し、舞台写真や芝居に関わる歴史文化を独自の視点で撮り続けている。歌舞伎、文楽、能、狂言、落語など古典芸能の他、文化風俗にもカメラを向ける。国立劇場、デュッセルドルフほかで写真展を開催。日本写真家協会・能楽写真家協会会員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
tama
elduquec
Shosei
なお