内容説明
男性のフリはやめました。女性装で話題の東大教授が見つけたのは「自分自身でないもののフリ」をすることは、すべての“暴力の根源”という発見だった!
目次
第1章 きっかけは
第2章 初めての経験
第3章 メディアを通じて
第4章 無縁の原理
第5章 歪んだ視点
第6章 美しさとは
著者等紹介
安冨歩[ヤストミアユム]
京都大学経済学部卒業後、株式会社住友銀行に勤務し、バブルを発生させる仕事に従事。二年半で退社し、京都大学大学院経済学研究科修士課程に進学。修士号取得後に京都大学人文科学研究所助手。日本が戦争に突入する過程を解明すべく満洲国の経済史を研究し、同時に、そのような社会的ダイナミクスを解明するために非線形数理科学を研究した。ロンドン大学の森嶋通夫教授の招きで、同大学の政治経済学校(LSE)のサントリー=トヨタ経済学・関係分野研究所(STICARD)の滞在研究員となる(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ネギっ子gen
69
【私は女装していません。しかし女性装しています。だって女性だから。それが私には、自然だから】トランスジェンダーを自認する東大教授が、女性装に至る来歴、その過程で感じたことや考えたことを綴った書。著者は、<さまざまの外部の力とぶつかりますが、それを恐れずに勇気を以って生きるべきであり、その試練から学び、成長することが、人間にとって最高の倫理だ/スピノザは、高名な哲学者には珍しい、とても優しい顔の人で、「有徳の無神論者」と呼ばれていたそうです。私もこのような優しい表情の学者になりたい、と切望しています>と。⇒2023/10/25
たま
50
読メで教えられた本。女性装をしている東大男性教員の著書、2015年刊、「トランスジェンダー」や「性同一性障害」(の問題点)について説明が分かりやすい。著者自身は「無理に分類すれば『トランスジェンダーでレスビアンの男性』」とのこと。前半は女性装、レーザー脱毛、髪染めの試みを振り返り、努力というか試行錯誤が写真からうかがえ面白い。日本人(男性)は学園祭だの各地のお祭りだので裸になること、女性装をすることに熱心だが、(外国では風習が違うので要注意)それについては三橋順子さんの研究があるらしい。2023/11/10
デビっちん
36
男女の性論だと思っていましたが、そんなチープなものではありませんでした。自分自身でないもののフリを我慢しているから、ツライしストレスも溜まります。自分自身であることを追求し自分らしくないものを省いていった結果、著者は男性のフリを辞めた、その過程が記載されていました。自分自身から離れていけばいくほど醜くもなるし、エネルギー量が低くなるようでした。そんな美しさを取り戻すためには、世間の常識という洗脳に立ち向かう勇気を持ち、怯えない心を育てる必要があると感じました。2018/01/08
ノンケ女医長
28
帯も含め、中にはたくさんの写真が掲載されている。過去から現在へ、あるべき姿に変わった自分自身の存在を、きちんと示したい姿勢が伝わる。本人は、とても楽しそう。ただ、著者の行動力から何かを学べるかは、判断が分かれるかも。作品には自己完結の表現が多く、当事者への助言や応援というスタンスでは、どうもなさそう。苦悩や生々しさが、希薄に感じた。2024/03/28
空のかなた
28
2015年発行。著者は東大東洋文化研究所の教授。身体は男性、恋愛対象は女性。心が落ち着く、自分が着たい服を選んでいたら自然と女性の服に行きついた。男装をやめ、スカートも履き、髭の永久脱毛をしたただけなのに「そういう趣味の方ですか?それともご病気の方ですか?」という不躾な質問がくる。日本社会は「立場」で出来ているから、役を果たさなければ「役立たず」と言われ立場を失う。だから役を果たすためならなんでもしないといけない、立場を守るためなら何をしてもいい、人の立場を脅かしてはならない、この著者の記述が心に刺さる。2023/11/04
-

- 電子書籍
- 異世界最高峰のギルドリーダー【分冊版】…
-
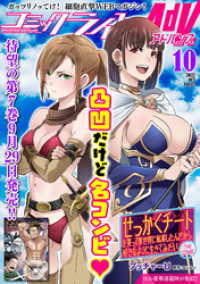
- 電子書籍
- コミックライドアドバンス2022年10…
-
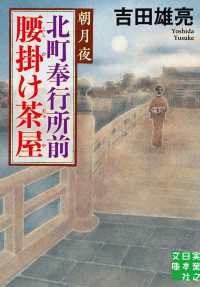
- 電子書籍
- 北町奉行所前腰掛け茶屋 朝月夜 実業之…
-
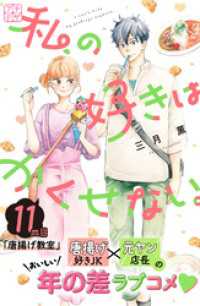
- 電子書籍
- 私の好きはかくせない。 プチデザ(11)
-

- 電子書籍
- 週刊アスキー No.1154(2017…




