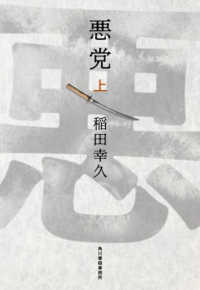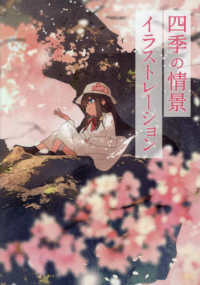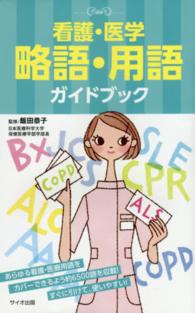著者等紹介
宮武健仁[ミヤタケタケヒト]
1966年大阪生まれ、徳島育ち。紀伊半島で水をテーマとして撮りはじめ、郷里の吉野川を中心に四国の水のある風景を撮り歩く。2009年に桜島の噴火を見て以来、大地のマグマの「赤い火」の迫力と、火山国の日本の各地にある地球の活動が感じられる風景と、その近くを流れる清流と、そこに暮らす光る生き物たちを追って全国を旅する。「日経ナショナルジオグラフィック写真賞2013」グランプリ受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ぶち
105
読友さんに紹介いただいた本。 恥ずかしながら、この本で初めて桜島が鹿児島湾に浮かぶ島で大隅半島とは地続きになっていることも、人口60万人の大都市からほんの数キロメートル先にあることも知りました。掲載されている写真はどれも火山としての桜島の雄々しく活発な姿を活き活きと伝えてくれています。火山雷の写真はすさまじいです。恐ろしくもありますが、すばらしく美しくもあります。噴火の際に感じられる空気、振動、音を臨場感たっぷりに伝えてくれる文章もよかったです。桜島をめぐる自然や人びとについても解説してくれています。2021/10/06
Aya Murakami
88
図書館本。 桜島には2010年のGWに家族旅行で行きました。薩摩半島側での噴煙をあげる桜島に直観で「歓迎されてる」と思った記憶があります。なお母と弟は結構怖がっていました…。 鹿児島市街地からの桜島の姿と大隅半島からの桜島の姿の違い。ちょっとニュアンスが違うかと思いますが、災害と恵み両方の側面を表しているような気がします。そして災害と恵みは紙一重だとも…。 阿蘇にも98年の家族旅行で行きましたが…、たしかに水蒸気が立ち上る火口でしたね。火口湖がきれいでした。2024/04/14
やま
85
鹿児島県桜島の赤く火を噴く噴火の様子と、それに伴って発生する火山雷を多くの写真を使って分かりやすく説明しています。噴火の時に火山雷が発生します。火山雷とは、火山噴火によってもたらされる雷のことで。火山が噴き上げる水蒸気、火山灰、火山岩などの摩擦電気により生じます。噴火の様子を見た事がありますが。火山雷は、初めて知りました。雷の小規模なものが、山頂の火口で溶岩の噴出時に閃光として光っているのは恐ろしいです。字の大きさは…大。2021.11.05読了。★★★☆☆2021/11/05
☆よいこ
82
科学読み物。徳島県にすむカメラマンの筆者は、阿蘇山で昔買った絵葉書が忘れられない。阿蘇山の火口が赤くなった写真で、その姿を見てみたいと思っていた。しかし阿蘇山では難しいので、鹿児島の桜島で火口が赤く光る瞬間を写真に取ろうとした。マグマが火口近くに上がってくると、上空の噴煙や火口を赤く照らすことがある。その現象を「火映(かえい)」という。地鳴り、山鳴りの鳴動を聞きながら火口を見続ける。2009年10月20日の噴火の瞬間を捉えた写真。2009年12月16日の噴火と火山雷の写真▽風景の違いを感じる。良本2022/10/01
yomineko@鬼畜ヴィタリにゃん💗
62
読み友様からのご紹介本です📙これはまた良い本に出会いました🌋徳島県在住のカメラマンさん、執念の撮影により桜島の噴火の画像が見れた!写真展を開くと、鹿児島市の方々にも大変珍しがられ喜ばれたらしいという貴重な画像の数々は一見の価値あり✨✨✨大正噴火以来1月12日には毎年避難訓練を欠かさないという。更に素晴らしいのは南九州の池、沼の透明度。四万十川よりも澄み切っているらしい😊2024/04/20
-
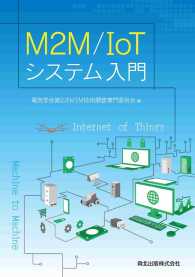
- 電子書籍
- M2M/IoTシステム入門