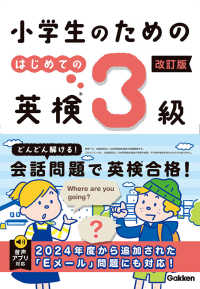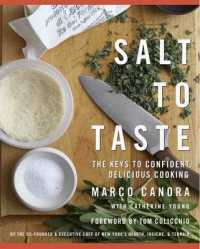出版社内容情報
様々な民族の言葉と、創作の言葉をコラージュふうに並べたテキストに、鮮やかな色彩の楽しい絵がつけられたユニークな絵本。言葉の多彩な響きも楽しい。
<読んであげるなら>3才から
<自分で読むなら>小学低学年から
内容説明
この絵本のことばは、作者の金関寿夫さんが、ご自身で創り出したことばと、様々な形ですでに存在していることばの響きとを、自在に組み合わせてできたものです。
著者等紹介
金関寿夫[カナセキヒサオ]
1918~1996年。島根県に生まれる。同志社大学英文科卒業。神戸大学、東京都立大学などの教授を歴任。ガートルード・スタインの詩、北米・インディアンの詩の紹介などをとおして、現代における言語芸術の可能性を探求する
元永定正[モトナガサダマサ]
1922年、三重県に生まれる。1955年、「具体美術協会」に入会(会は’72年に解散)以後、モダンアートの世界で、国際的に活躍。1964年、1965年、現代日本美術展にて優秀賞受賞。1983年第4回ソウル国際版画ビエンナーレでグランプリ受賞。同年第15回日本芸術大賞受賞
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ヴェネツィア
261
金関寿夫・文、元永定正・絵。これはとっても珍しい絵本。なにしろ、全ページにわたってオノマトペだけで構成されているのだから。お話は、あるといえばある。ないといえばない。おそらくは自分で自由に作るのだろう。さすがに、これだけのページ数をオノマトペだけで埋めるのは作者も苦労したようで、あちこちから寄せ集めてきた。そして、絵がまた意表をついていて、これまた全てが抽象画である。最も具象的なのが、表紙のカニというレベル。さて、子どもたちの評価やいかに。2025/05/05
スシローよりはま寿司が好きな寺
54
これは楽しい絵本。言語の実験的手法の難解な絵本だとするのはダサい。昔の筒井康隆やタモリ一派のハナモゲラ語ブーム的な気運から生まれたのかも知れないが、理屈無しに楽しんで読むべきである。ストーリーなんて無い。表紙のこれをカニだと思うにも無理がある。とにかく意味不明なフレーズが出てきて、読む者に独特のリズム感をくれる。巻末を見るといろんなものから引用しており、インテリが作った絵本だとわかるが。お薦めはしないが、一見の価値はある。2016/09/07
みっくす
40
1歳9ヶ月。もう少し小さいときに読んだ方が良かったかな。それか大きくなってからか…。言葉遊びの絵本だが、理解できない言葉たちが怖いようで、絵本を閉じてしまいました。それだけ言葉が分かるようになったという証拠だね。2017/11/27
♪みどりpiyopiyo♪
34
音が楽しい赤ちゃん絵本です。声に出して読むと、くちびるがコショコショくすぐったいのも楽しいね♪ 福音館書店の「こどものとも」ってこういう冒険心というか遊び心を感じさせる絵本を出してくれるから好き。■カラフルで不思議な音だらけの絵本。あれこれ考えず リズムと音を楽しんで読むのがおすすめです。一番最後のページに、絵本の中に出てくる言葉の意味の説明が。絵本の最初の「カニ ツンツン〜」はアイヌの人の聴き取りによる鳥のさえずりの声なんですって♪
gtn
22
すべては「カニツンツン」というアイヌの言葉の響きから始まったか。それが、アメリカ幼児語、イタリアやモーツァルト歌劇等全世界に広がっていく。その国、その地域で発する音をつなげると、リズムになり、音楽となる。ひいては人間平等のシンボルとなる。(いや、おそらくそんな大層な意味は込められていない。)2022/07/19
-

- 電子書籍
- 教育虐待17 Vコミ
-

- 電子書籍
- 老年の読書(新潮選書) 新潮選書