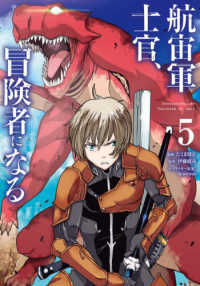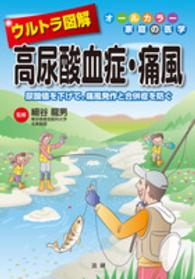内容説明
日本建築界の巨星、故村野藤吾氏が、現代人に残した、最後の対話集です。自身が手がけた作品の細かな解説をはじめ、難解といわれる氏の建築哲学を、平易な言葉でわかりやすく語っておられます。
目次
第1回講座 設計の責任者(塾生の自己紹介と抱負;卒業して自由な大阪へ ほか)
第2回講座 建築とは何か(様式を乗りこえて;生いたちの記 ほか)
第3回講座 建築家とは何か(建築家の資質;建築家と幾何学 ほか)
第4回講座 建築の哲学(綿業倶楽部の図面をみながら;窓のデザイン ほか)
著者等紹介
村野藤吾[ムラノトウゴ]
1891年、佐賀県唐津市生まれ。1918年早稲田大学卒業。渡辺節建築事務所に入り、折衷主義の様式建築を手がける。綿業会館の設計を最後に、1933年独立、村野建築事務所を設ける。1955年日本芸術院会員に推挙される。代表作には、大阪そごう百貨店、大阪新歌舞伎座、京都比叡山ホテル、都ホテル、神戸大丸百貨店…など、有名建築物が多い。1984年、逝去(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
パダワン
9
1980年の「なにわ塾」での対話式講演の記録。 建築史家の長谷川尭さんがコーディネーターとして参加者と村野さんを繋いでくれる。 設計者として心に残る言葉はいろいろあった。 99%は施主の意向、残りの1%に村野の意思がある、という言葉。他でも良く聞くのだけど、ご本人が発していらっしゃるのをこの本で直に目にして意味がわかるような気がする。 施主の意向は諸条件の一つでしかなくて、それを当然全て満たした上に創作の本質はある。 つまりは研鑽や検討がもっともっとできるということ。 設計者として居住まいを正す。2024/06/15
J
3
売れる建築を作る(≒クライアントや社会に対して真に寄与できることがまず第一)、設計の99%はクライアントのために、残った1%は村野でしかできないことを行うために、など。職業的建築家としてかくあるべしという精神が勉強になった。2024/05/31
Soichiro Higuma
1
村野藤吾氏の建築に対する考え方が非常によく分かる本.難しいことも換言して,分かりやすく伝えることを心掛けていた氏の態度に感服.ただ30年も前の対話集なのでよく分からない部分も多々あった.数ある言葉のなかで「99%は人の言うことを聞きなさい。あと1%が結局、建築家の考え方が出て来ているんだ。」というのが謙虚で素敵だなと思った.2018/04/26
ponnnakano
1
以前読んだレンゾ・ピアノと安藤忠雄との対談本でピアノが言っていた事とほぼ同じ事を既にずいぶん昔に、村野さんが話してました。 「その人の考えを理解するのは、ある時代には建築家の卑屈な態度であったが、そんなことはない。その人のイメージを診断するのだから。診断はいくら厳密であって、どんなに手間をかけても構わない、そのかわり薬は医者にお任せ下さいと言える訳です。」 謙虚さと自分の技倆への自負がないとなかなか難しいことだけど、誰もがこうするように心がければいいのにな、と思いました。2014/01/26