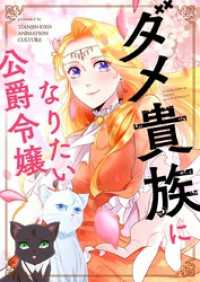出版社内容情報
ニューロダイバーシティという言葉を聞いたことはありますか?
人と話すのは苦手でも、絵やダンスで思いを鮮明に伝えられる人がいます。
ちょっとした音や光で激しく動揺してしまうけど、心が休まる環境さえ与えられれば、高度な計算やプログラミングにずば抜けた能力を発揮する人がいます。
ーー発達障害や自閉症と診断される「非定型」な人は、「標準的」な能力を持つ人とは違うとして「区別」されてきました。しかし、これからは両者が「混ざる」ことでこそ社会が変化します。
脳神経の多様性、すなわちニューロダイバーシティのありかたを教育に実践する二人が語る多様性社会の最新デザイン。
これからの教育から地域社会、組織を前進させるための、「普通」をずらしていくドキュメントです。
【出版社からのコメント】
教育のパラダイムシフトが起きようとしています。ニューロダイバーシティという新しい考え方によって。脳神経(ニューロ)の多様性(ダイバーシティ)を尊重する環境を、学校がデザインすることでどんな奇跡が生まれるのか。
未来を提言し続ける伊藤穰一さんと、先進的な教育実践者・松本理寿輝さんによる、刺激的な一冊です。
内容説明
個性を「分ける」から「混ぜる」へ。最新ダイバーシティの教科書!
目次
序章 ニューロダイバーシティとは何か?
第1章 「変わってる」を肯定する保育園
第2章 ダイバーシティはなぜ必要なのか
第3章 「孤育て」から「共育て」へ
障害とのつきあい方は一つじゃない―アーティストfuco:さんの母 瀬戸口庸子さんに聞く
第4章 「ニューロダイバーシティの学校」を作る
第5章 web3はニューロダイバーシティに何をもたらすのか
「好き」や「得意」の種火に、風を送り込むように―心理発達相談員・スクールカウンセラー 大庭亜紀さんに聞く
終章 「経験」が求められる時代へ
著者等紹介
伊藤穰一[イトウジョウイチ]
1966年生まれ。ベンチャーキャピタリスト、起業家、作家、学者として、主に社会とテクノロジーの変革に取り組む。2011年から2019年までは、米マサチューセッツ工科大学(MIT)メディアラボの所長に奉職。非営利団体クリエイティブコモンズの最高経営責任者のほか、ニューヨーク・タイムズ、ソニー、ナイト財団、マッカーサー財団、ICANN、Mozilla財団の取締役を歴任した。2023年より千葉工業大学学長
松本理寿輝[マツモトリズキ]
1980年生まれ。2003年一橋大学卒業、博報堂入社。不動産ベンチャーを経て、かねてからの構想の実現のため、2010年ナチュラルスマイルジャパン株式会社を設立。認可保育所「まちの保育園」、認定こども園「まちのこども園」を都内6カ所にて運営。保育の場をまちづくりの拠点として位置づけ、豊かな社会づくりをめざしている。レッジョ・エミリア・アプローチ国際ネットワークの日本窓口団体「JIREA」の代表もつとめている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
きゅー
かるろ
やそん
tangent
mitsuhiro