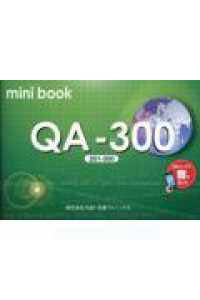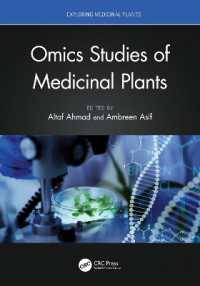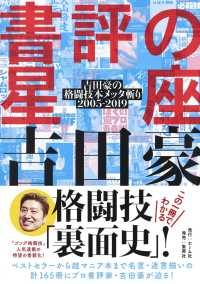出版社内容情報
●商品の説明
障がいがある人々が着る洋服の選択肢の少なさ/生理のタブー視とコミュニケーションの閉鎖性/間違いを許し合えない不寛容による生きづらさ/コミュニティの弱化による暮らしの質の低下/地域の資産を活用しきれていない(CASE 7 静岡市プラモデル化計画/脱炭素社会に向けた、生活者の具体的なアクションが実践されていない……。
日々の生活のなかで、博報堂チームは何を課題と捉え、具体的にどんなアクションを起こしたのか―?。
【当事者】と【当事者の外にいる人々】、そして【社会】をつなげるクリエイティビティで社会課題に挑んだ、11のドキュメント!
●目次
・PROLOGUE
嶋 浩一郎(博報堂 執行役員/博報堂ケトル 取締役 クリエイティブディレクター/編集者)
・INTERVIEW 1
近山知史(博報堂 エグゼクティブクリエイティブディレクター)
・CASE STUDY
「社会課題」×「クリエイティビティ」 11のケーススタディ
CHAPTER 1 生きる、を変える
#01 答えのない道徳の問題 どう解く?
#02 キヤスク
#03 テレビ東京「生理CAMP」
#04 注文をまちがえる料理店
・INTERVIEW 2
水野祐(法律家/弁護士(シティライツ法律事務所)
・CASE STUDY
CHAPTER 2 暮らす、を変える
#05 ノッカル
#06 茶山台団地再生プロジェクト
#07 静岡市プラモデル化計画
#08 shibuya good pass
・INTERVIEW 3
ティム・ブラウン(kyu 副会長/IDEO 共同会長)
・CASE STUDY
CHAPTER 3 つくる、を変える
#09 大好物醤油
#10 Earth hacks
#11 東京〇〇入門BOX
・EPILOGUE
川崎レナ(国際的NGO「アース・ガーディアンズ」日本支部代表)
× 小谷知也(『WIRED』日本版 エディター・アット・ラージ)
内容説明
日々の生活のなかで、彼ら/彼女らは何を課題と捉え、具体的にどんなアクションを起こしたのか。クリエイティビティで社会課題に挑んだ博報堂チームによる11のドキュメント!
目次
CASE STUDY 「社会課題」×「クリエイティビティ」11のケーススタディ(生きる、を変える;暮らす、を変える;つくる、を変える)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
tuppo
マーモ
Tim
酢
やさい