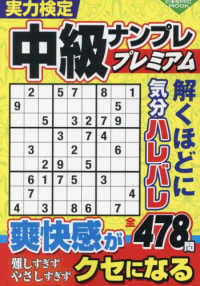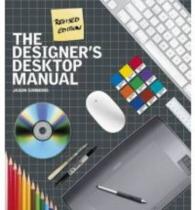内容説明
センスメイキングは、人文科学に根ざした実践的な知の技法である。アルゴリズム思考の正反対の概念と捉えてもいいだろう。
目次
序 ヒューマン・ファクター
第1章 世界を理解する
第2章 シリコンバレーという心理状態
第3章 「個人」ではなく「文化」を
第4章 単なる「薄いデータ」ではなく「厚いデータ」を
第5章 「動物園」ではなく「サバンナ」を
第6章 「生産」ではなく「創造性」を
第7章 「GPS」ではなく「北極星」を
第8章 人は何のために存在するのか
著者等紹介
マスビアウ,クリスチャン[マスビアウ,クリスチャン] [Madsbjerg,Christian]
ReDアソシエーツ創業者、同社ニューヨーク支社ディレクター。コペンハーゲンとロンドンで哲学、政治学を専攻。ロンドン大学で修士号取得。現在、ニューヨークシティ在住
斎藤栄一郎[サイトウエイイチロウ]
翻訳家・ライター。山梨県生まれ。早稲田大学卒(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。