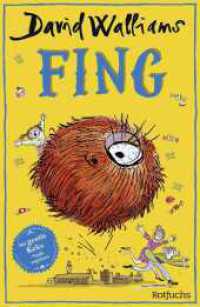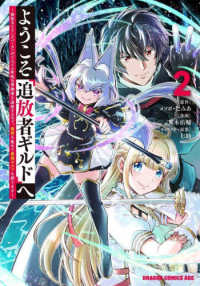目次
第1章 誰にでも発想力はある
第2章 知覚の壁―正しいものの見方を妨げる壁を破る
第3章 感情の壁―発想をブロックする感情の壁を破る
第4章 文化と環境の壁―創造的思考における「非」まじめのすすめ
第5章 知性と表現の壁―思考の道具を使いこなそう
第6章 壁を破るテクニック1―思考言語を使い分けよう
第7章 壁を破るテクニック2―知的に楽しみながら壁を破ろう
著者等紹介
アダムス,ジェイムズ・L.[アダムス,ジェイムズL.] [Adams,James L.]
スタンフォード大学名誉教授。1966年よりスタンフォード大学にてメカニカルデザイン、プロダクトデザインを教える。Industrial Engineering and Engineering Management(現Management Science and Engineering)学部チェアマン、Stanford Program in Values、Technology、Science、and Societyチェアマンなどを歴任
大前研一[オオマエケンイチ]
早稲田大学卒業後、東京工業大学で修士号を、マサチューセッツ工科大学(MIT)で博士号を取得。マッキンゼー・アンド・カンパニー・インクを経て、現在(株)大前・アンド・アソシエート代表取締役、(株)ブレーク・スクール代表取締役、UCLA大学院政策・社会研究学部教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
みんと
9
頭の固い人は問題に直面した時に言葉の通り固まり、突破口を見いだせないままになってしまう。 発想の転換は非常に大切であり、正しいやり方、考え方すればうまく解決策も出てくるはずである。 ここで紹介されている方法により、頭の中のアイデアが形成されていくプロセスを理解し、頭がどう機能しているのかを知り、ヒントを得ることができれば楽な気持ちになれると思うのだが、まずは学習として実践する事が大切である。2013/08/21
一休
5
古い本なのか、なかなか読みにくかった。発想するときに思い込みや盲点があるよね、その壁を壊そうね、という内容。壁の種類は、知覚、感情、文化と環境、知性と表現の4つ。2025/03/18
AKI
2
問題の解決とは、つまり、無秩序な状態を秩序づけることである。したがって、秩序を求める欲求は自然の成り行きなのだ。その一方で、無秩序を許容できることも必要不可欠である。2022/10/14
ゆう
2
★★★★★ 発想や思考に制限をかける6つの壁を可視化してくれる。『幽霊の正体見たり枯れ尾花』ではないが、壁を明確に認知することで対処法は自ずと見えてくる。もちろん本書内にも壁の壊し方が紹介されている。思考停止になった瞬間から、誰かの都合の良い駒になる。そうならないためにも、思考の壁を知り思考のエンジンを常に回すためのガソリンとなる一冊だ。これからますます、イノベーションが大切になる。そんな未来を乗り切るための指南書として最適である。読まないと損な本である。2019/09/19
ますみ
2
発想・発見・理解・解決の障害として、認知、感情、文化・環境、知性・表現があると主張している。後半は、主に知性・表現の訓練と対処が紹介される。文化・環境の対策は少なく、特に文化については記載がない。 筆者は、文化の壁は暗黙の慣習などから起こる感情の壁として現れると捉えられていると想像される。また、それは納得できる。その文化の壁を減らすには慣習を表に出し環境としてコントロールするという方法があると思った。演習で、数学的には回答が難しいと言及された問題があったが中間値の定理だなって思った。2016/05/25
-

- 和書
- 虚構と現実の間に