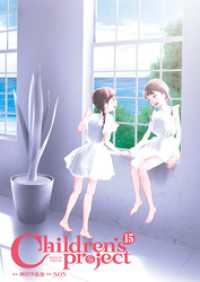内容説明
生物としてのヒグマ・ヒグマと人との関わり・現代社会におけるヒグマを巡る諸問題を考える、分野を超えた総合的学問「ヒグマ学」初の解説書。
目次
第1部 ヒグマの自然史(ヒグマの生態;ヒグマの飼育からわかること;ヒグマの多様性と進化 ほか)
第2部 ヒグマと人類史(ヒトとヒグマの考古学―“儀礼行為”を遡る;日本の古代社会とクマ信仰;クマと人間の儀礼的関係―動物の魂送り ほか)
第3部 ヒグマと現代社会(ヒグマの今―世界のヒグマ日本のヒグマその現状と共存への課題;知床、ヒグマと生きる地域社会を目指して;ヒグマと法律 ほか)
著者等紹介
天野哲也[アマノテツヤ]
1947年生まれ。1971年同志社大学文学部文化史学科卒業。1978年北海道大学大学院文学研究科日本史学専攻博士課程。単位取得退学。北海道大学総合博物館助教授。文学修士
増田隆一[マスダリュウイチ]
1960年生まれ。1989年北海道大学大学院理学研究科博士課程修了。北海道大学創成科学共同研究機構助教授。理学博士
間野勉[マノツトム]
1960年生まれ。1992年北海道大学大学院農学研究科博士課程修了。北海道環境科学研究センター主任研究員兼野生動物科長。博士(農学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
たまこ
1
今年は熊による害が北海道でも本州でも問題になってますが、20年ほど前の北海道大学の講義録を元に書かれた本です。生物にとどまらず文化にどのようにヒグマが関わってきたかまで語られています。 20年ほど前はヒグマは数を増やすべき保護動物として見られていたことが印象的ですが、それでも人との接点をどうしていくかはすでに課題になっていたことがわかります。新世代ベアーズ今じゃ増えています。2023/11/12
j1296118
0
ルーカンを抱き殺すアーサー王は最期に至って熊の粗暴性を取り戻してしまった姿、と2017/11/12
しまたろう
0
ヒグマのことを書いた本はたくさんある。入門という名が付いているからといって、これをはじめに読まねばならぬわけではない。しかし学識者が共著した一般向けの本は多くはないかもしれない。そういう本の良いところは、客観的である点だと思う。
sunaba
0
北大のオムニバス講義を書籍化したもの。生物学的なアプローチの第1部、人文学的なアプローチの第2部、そしてよりアクチュアルな問題を取り上げた第3部という3部構成。興味があるところだけを読む形でもよいだろう。個人的には基本的知識が得られる第1部がおもしろかった。2024/01/20
モンジー
0
途中をさらっと読んだだけで返却2019/09/21