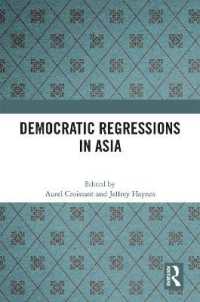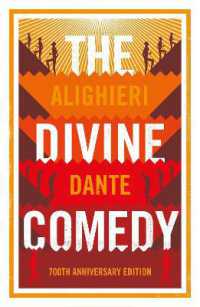出版社内容情報
「中国古典を自分の力で読んでみたくはありませんか」
注釈を利用して古典を読む。その手法を基礎と実践で学ぶための一冊です。
【基本篇】で、注釈の基本知識と、テキスト、辞書、参考書について学び、
【読解篇】で儒教経書である『孝経』『論語』『周易』『尚書』『詩』『礼記』『春秋左氏伝』の注釈を実践的に学びます。
「「注釈を利用して古典を読む」というこの方法を身につけることができれば、儒教経典のみならず、諸子の書・歴史書・文学作品・仏教や道教の経典に対する注釈、そして日本において作られた漢文の注釈書などに対しても、広範に応用してゆくことも可能です。そのためにも、まず儒教経典の注釈の読み方を学ぼうではありませんか。」(「はじめに」より)
[本書の構成]
はじめに
【基本篇】
第一講 古 典
第二講 注 釈
第三講 『十三経注疏』の概要
第四講 字 形―文字学
第五講 字 音―音韻学
第六講 字 義―訓詁学
第七講 辞 書
第八講 句読・文法
【読解篇】
第九講 『孝経』の注を読む
コラム『孝経』―誰もが学ぶ儒教経典
第十講 『論語』の注を読む
コラム『論語』―古注と新注
第十一講 『周易』の注疏を読む
コラム『周易』―十翼をめぐって
第十二講 『尚書』の注疏を読む
コラム『尚書』―現行本から遡る
第十三講 『詩』の注疏を読む
コラム『詩』―『毛詩』以外の『詩』
第十四講 『礼記』の注疏を読む
コラム『礼記』―四十九篇の複雑さ
第十五講 『春秋左氏伝』の注疏を読む
コラム『春秋』―孔子の筆削をめぐって
おわりに
参考文献一覧
附 録(一) 訓詁のいろいろ
附 録(二) 多音字挙例
附 録(三) ピンインつき本文
内容説明
中国古典を自分の力で読んでみたくはありませんか。注釈を利用して古典を読む手法を基礎と実践で学ぶ。
目次
基本篇(古典;注釈;『十三経注疏』の概要;字形―文字学;字音―音韻学 ほか)
読解篇(『孝経』の注を読む;『論語』の注を読む;『周易』の注疏を読む;『尚書』の注疏を読む;『詩』の注疏を読む; ほか)
附録
著者等紹介
古勝隆一[コガチリュウイチ]
1970年生まれ、福岡県出身。東京大学文学部中国哲学科卒業、同大学院人文社会科学研究科博士課程修了。博士(文学、東京大学)。京都大学人文科学研究所助手、千葉大学文学部助教授、京都大学人文科学研究所准教授を経て、京都大学人文科学研究所教授。専攻は中国古典学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
崩紫サロメ
さとうしん
電羊齋
PETE
夜桜銀次