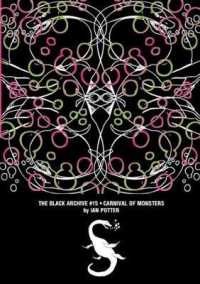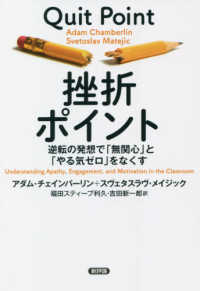内容説明
世俗社会を動かす真宗の世界。大名権力が脅威に感じつつも頼らざるをえなかった真宗の存在。13編の論考がその種々に迫る。
目次
1 戦国争乱と本願寺(上杉謙信と笠原本誓寺―真宗寺院という戦国大名の外交チャンネル;三河一向一揆後の本願寺門徒衆の動向;本願寺と鉄砲;織豊期本願寺の起請文にみる神仏)
2 中近世移行期と本願寺(益田照従―本願寺と豊臣政権に仕えた家臣;本行寺准如と北陸門徒;本願寺教如をめぐる女性門徒について;本願寺教如と織豊武士の茶の湯―慶長期豊臣家家臣団との関係を中心に;美濃地域の真宗寺院と織豊武士団―由緒書を中心に)
3 近世本願寺の諸相(近世京都の都市開発からみる傾城町―隣りあう六条三筋町と東本願寺;近世地域真宗寺院の一齣―野崎専応寺を例に;真宗寺院の由緒書にみる統一権力像;親鸞伝の史実と伝承―親鸞伊勢参宮伝承をめぐって)
著者等紹介
草野顕之[クサノケンシ]
1952年、福岡県生まれ。大谷大学文学部史学科卒業、大谷大学大学院文学研究科博士後期課程満期退学。博士(文学)。大谷大学文学部史学科専任講師、助教授、教授および大谷大学学長(2010‐16年)を歴任。現在、大谷大学名誉教授。佛教史学会会長。専門は日本仏教史(中世)・真宗史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 電子書籍
- 晋遊舎ムック 便利帖シリーズ001 L…