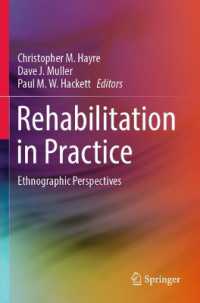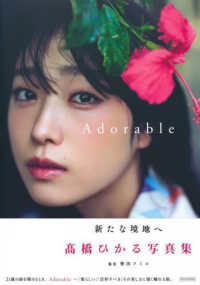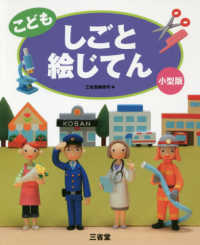出版社内容情報
敦煌、龍門、さらに中国各地の仏教美術の整理・編年を行うことにより、初唐期と盛唐期の様相を解明する意欲的研究。図版500点余。――「安史の乱」によって国内が大混乱に陥る以前、中国仏教美術は西安を中心にその頂点に達し、彫刻や絵画作品は、完成した様式、形式を獲得した。またそれが統一様式、形式となり、各地で類似した像が多数造られ、北魏後期に始まった地域性がここにおいて解消された。もっとも華やかなこの時期の中国仏教美術史研究は、日本においても中国においても盛んで蓄積が多く、多くの問題がすでに解決されている」というのが、筆者の唐仏教美術に対する漠然とした印象であった。しかし、実際に自らこの時期の仏教美術研究をしてみると、果たして統一様式、形式なるものが、本当に存在するのか、そもそも何をもって統一様式、形式とするのかという問題が生じただけでなく、基本的でありながら定説のない重要な問題が、未だ少なからず存在していることに気づくようになった。そのひとつに時代区分の問題がある。(以上、本書「序」より)
本書は、『雲岡石窟文様論』(2000年)、『中国仏教美術と漢民族化―北魏時代後期を中心として』(2004年)、『中国仏教造像の変容―南北朝後期および隋時代』(2013年)につづく、著者の第4冊目の研究書となる。
本書では、敦煌莫高窟、龍門石窟といった大規模な石窟はもちろんのこと、中国各地に点在する仏教美術をも視野に入れ、現存(または写真資料)する仏教美術作品を分析精査することにより、作品の整理、編年を行い、その結果を比較し総合することで、唐前期の仏教美術の様相を明らかにすることを目的とする。このことが、唐前期における初唐期と盛唐期武侠美術の性格の違いの理解に繋がり、時代区分にゆれる則天武后期の評価を可能にした。
さらに唐前期のどの時期に仏教美術表現が頂点に到達したか、またそれらの様式およびそれを具現するための形式が、仏の姿の真の表現として人々に受容され、全国規模の「統一様式、形式」として成立したかどうかなどの問題を明らかにする。
口絵
序
第一部 敦煌莫高窟における唐前期浄土表現の展開
第一章 初唐期初期第57窟、第322窟に見られる過渡的性格
はじめに
一 隋第三期諸窟
二 唐前期第一期窟(第57窟)
三 唐前期第一期窟(第322窟)
四 敦煌莫高窟唐前期第一期諸窟の特徴
おわりに
第二章 第220窟に見られる大画面の西方浄土変相図の出現
はじめに
一 窟形式と西壁
二 南壁西方浄土変相図
三 北壁薬師浄土変相図
四 敦煌莫高窟における浄土図
五 第220窟南北壁浄土変相図の成立過程
六 東壁維摩経変相図
七 第220窟のシンボリズム
おわりに
第三章 西方浄土変相図における初唐期から盛唐期への展開
はじめに
一 唐前期第二期諸窟の西方浄土変相図
二 唐前期第二期の大画面西方浄土変相図
三 唐前期第三期諸窟の西方浄土変相図
四 唐前期第四期西方浄土変相図
五 唐前期第三、第四期諸窟西方浄土変相図の構図と外縁部の関係
六 構図以外の西方浄土変相図の特徴
おわりに
第二部 龍門石窟唐前期諸窟の編年と造像の特徴
第一章 唐窟造営の始まりとしての賓陽南洞と造像の特徴
はじめに
一 第159窟(賓陽南洞)正壁造像
二 第159窟(賓陽南洞)本尊の尊格
三 龍門石窟における隋時代の造像
四 第159窟(賓陽南洞)における無紀年銘大龕
五 第159窟(賓陽南洞)における貞観年銘龕
六 第159窟(賓陽南洞)造営再開時の工人系統と小龕開窟状況
七 第242窟(騰蘭洞)
おわりに
第二章 敬善寺洞地区の石窟編年と造像に見る特徴
はじめに
一 龍朔元年銘第331窟(韓氏洞)
二 龍朔元年以前の造像で第331窟(韓氏洞)と関係する造像を持つ窟
三 龍朔元年前後の造営で第331窟(韓氏洞)と関係する造像を持つ窟龕像
四 第362窟(袁弘績洞)
五 第403窟(敬善寺洞)
六 第242窟(騰蘭洞)から第403窟(敬善寺洞)までの流れ
七 第403窟(敬善寺洞)のシンボリズム
おわりに
第三章 第1280窟(奉先寺洞)の唐前期窟における位置づけ
はじめに
一 第1280窟(奉先寺洞)の概要
二 第565窟(恵簡洞)
三 第555窟(蔡大娘洞)、第557窟(清明寺洞)
四 第543窟(万仏洞)
五 第543窟(万仏洞)のシンボリズム
六 第1280窟(奉先寺洞)と第543窟(万仏洞)
おわりに
第四章 西山南端諸窟龕の編年と龍門石窟における二系統の工人集団
はじめに
一 第1931窟(龍華寺洞)の概要
二 第1931窟(龍華寺洞)の造営年代
三 第1955窟(極南洞)
四 第1628窟(八作司洞)
五 第1628窟(八作司洞)の造営年代
おわりに
第五章 龍門石窟唐前期諸窟中に見られる浄土表現について――第2144窟(高平郡王洞)および第2139龕(西方浄土龕)を中心として――
はじめに
一 第2144窟(高平郡王洞)
二 阿弥陀五十菩薩像
三 第2139龕(西方浄土変龕)
四 山西省高平県羊頭山石窟および忻州市静楽県浄居寺石窟
五 第2144窟(高平郡王洞)と第2139龕(西方浄土変龕)
六 第2055窟(擂鼓台中洞)における浄土表現
おわりに
第三部 中国各地の唐前期造像
第一章 山東地方における唐前期造像の様相
はじめに
一 済南神通寺千仏崖
二 東平県理明窩摩崖
三 雲門山石窟
四 駝山石窟第1窟像
五 済南市県西巷の開元寺址
六 山東地方の唐前期造像
おわりに
第二章 山西地方天龍山石窟唐前期諸窟の編年と造像の特徴
はじめに
一 東峰諸窟
二 西峰諸窟
三 天龍山石窟唐代窟の編年(第4窟、第14窟、第18窟、第17窟)
四 天龍山石窟唐代窟の編年(第6窟、第21窟)
おわりに
第三章 河北地方における唐前期の仏教造像の展開
はじめに
一 南宮後底閣遺址出土白玉造像
二 南宮後底閣遺址出土五角形白陶仏龕
三 ?台市柏郷県崇光寺址出土如来坐像
四 曲陽修徳寺址出土白玉造像
五 房山雲居寺三公塔周囲の唐白玉塔如来坐像
六 唐前期河北造像の様式、形式変遷
おわりに
第四章 西安宝慶寺塔石像龕と同時期の他地域造像について
はじめに
一 宝慶寺塔「倚坐像龕」グループ
二 宝慶寺塔「成道像龕」グループ
三 宝慶寺塔「施無畏印像龕」グループ
四 宝慶寺塔「倚坐像龕」「成道像龕」「施無畏印像龕」の関係
五 宝慶寺塔石像龕主尊の尊格
六 西安およびその付近の703年頃の造像
おわりに
第五章 初唐期における仏教造像の展開――西安造像様式、形式の受容に着目して――
はじめに
一 陝西省旬邑県馬家河石窟中心塔窟
二 炳霊寺石窟第53龕、第54龕、第56龕
三 浚県千仏洞第1窟
四 慶陽北石窟寺第32窟
五 須弥山石窟
六 670年代から則天武后期における各地の仏教造像の様相
七 則天武后期終了以降、中宗・睿宗時期の如来像
おわりに
第四部 結論
一 敦煌莫高窟唐前期の浄土変相図の特質
二 龍門石窟唐前期造像の流れ
三 唐前期の中国各地の仏教造像の様相
四 則天武后期および中宗・睿宗時期の仏教美術の特質
おわりに
あとがき
付録
図版一覧
中文要旨
索引
八木春生[ヤギ ハルオ]
著・文・その他
目次
第1部 敦煌莫高窟における唐前期浄土表現の展開(初唐期初期第五七窟、第三二二窟に見られる過渡的性格;第二二〇窟に見られる大画面の西方浄土変相図の出現;西方浄土変相図における初唐期から盛唐期への展開)
第2部 龍門石窟唐前期諸窟の編年と造像の特徴(唐窟造営の始まりとしての賓陽南洞と造像の特徴;敬善寺洞地区の石窟編年と造像に見る特徴;第一二八〇窟(奉先寺洞)の唐前期窟における位置づけ ほか)
第3部 中国各地の唐前期造像(山東地方における唐前期造像の様相;山西地方天龍山石窟唐前期諸窟の編年と造像の特徴;河北地方における唐前期の仏教造像の展開 ほか)
第4部 結論
著者等紹介
八木春生[ヤギハルオ]
1961年横浜に生まれる。1988年に国際基督教大学大学院比較文化研究科修士課程修了後、成城大学大学院文学研究科美学美術史専攻博士課程後期に入学。1993年に単位取得退学。1985年から1年間、スイス国立ベルン大学哲学・歴史学部に留学、1988年から2年間、北京大学考古系に留学。1998年博士(文学)取得。現在、筑波大学芸術学系教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。