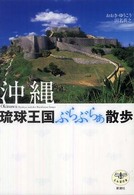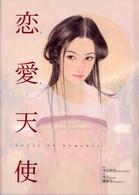出版社内容情報
仏教学・歴史学などの幅広い視野より「法会と仏道」の意義を明らかにするとともに、震災での僧侶の活動から仏道の現代的意義を問う。日本仏教研究のための新たな視座を提起。
仏教学・法会学・歴史学・建築学などの幅広い視野より伝統ある「法会と仏道」の意義を明らかにするとともに、東日本大震災における仏教者(僧侶)の活動を通じて、仏道の現代的意義を問う。
----------
この度の研究プロジェクトにおいて推進する「南都学・北嶺学」の中核は、あくまでも「仏教学」にあり、南都六宗の教学ならびに天台教学についての研究を深め、進展させることにあります。しかし、日本の仏教を教学展開の観点からのみ見たのでは、その実体を把握することはできません。なぜならば、日本仏教がさまざまな展開を見せることによって多種多様な「学問」や「芸道」が生み出され、それがまた日本仏教に新たな展開をもたらしているからです。そこで、この度の研究プロジェクトにおいては、単に「南都・北嶺の仏教」とはせず、「南都学・北嶺学」の造語をあえて用いることにしました。したがって、今回創始した「南都学・北嶺学」には、まだ学問体系がありません。まずは「南都学」「北嶺学」という大きな入れ物を作り、その中に種々の「学体系」を有した諸学問・諸文化を盛り込んでいくところに、新たな知見が獲得されるであろうことを企図しています。この点に実は、「南都学・北嶺学」の名称を創始した意義と意図があるのです。
(「序文」より)
----------
※2017年6月3、4日に薬師寺食堂で開催された国際シンポジウムの内容をもとに書籍化。
龍谷大学アジア仏教文化研究叢書6
序 文──南都学・北嶺学の構築に向けて──(楠 淳證)
第?部 法会と論義
中世南都諸寺の法会──講説・論義・打集を中心に──(永村 眞)
一 はじめに
二 寺院と法会
三 南都の法会
四 法会と聖教
五 むすび
法相論義と仏道──「一仏信仰」か「多仏信仰」か──(楠 淳證)
一 はじめに
二 論義「一仏?属」の伝統説
三 日本での法相論義「一仏?属」の展開
四 貞慶による一仏?属否定の論理と意義
五 むすび──「一仏信仰」と「多仏信仰」
?薬師寺の法会――慈恩会
第?部 法会の空間
法会と講式──南都・北嶺の講式を中心として──(ニールス・グュルベルクNiels GUELBERG)
一 はじめに
二 講式の原点──横川首楞嚴院二十五三昧式
三 三つの基本概念──講、講会、講式
四 講式の歴史的展開
五 源信作の鎌倉期における継承──慈鎮和尚慈円
六 南都の代表者──解脱房貞慶と講式
七 むすび
歌人の儀式の『月講式』──鴨長明と道元における三界唯心──(フレデリック・ジラール Frederic GIRARD)
一 はじめに
二 三界唯心
三 鴨長明の『方丈記』による隠遁
? 鴨長明の恨み
? 南方熊楠の見た長明──世界と人生に理解できない不思議
? 人間の疎外と身心の不可離な関係による自由
四 鴨長明の自由の発見
五 『月講式』──一心、法界、月
六 むすび
法会と仏堂(藤井恵介)
一 寺院と伽藍の形態
〈インド〉〈中国〉〈日本〉
二 古代の寺院──法会と建築
三 密教法会の開始
四 礼堂の創設
五 中世の寺院──法会と建築
六 祖師堂の成立
七 禅宗における僧堂、律宗における僧堂
?薬師寺の法会――修二会花会式
第?部 僧の生活と持律
北嶺の戒律──実導仁空を中心に──(ポール・グローナー Paul GRONER)
一 はじめに
二 小乗戒と大乗戒
? 日本天台に対する挑戦──俊?
? 『法華経』と開会のアプローチ
? 『涅槃経』の役割
三 戒体について
四 むすびにかえて──付論
南都の戒律──中世の復興から現代を考える──(蓑輪顕量)
一 はじめに
二 中世の戒律復興
三 現代の東大寺における授戒
四 通受普及の時期
五 近世、東大寺における具足戒受戒
六 むすび
親鸞と戒律──無戒名字の比丘──(玉木興慈)
一 はじめに
二 親鸞の仏教の特徴
三 『末法灯明記』に見る「無戒名字」の「比丘」
四 真仏弟子と常行大悲
五 むすびにかえて
?薬師寺の法会――弥勒縁日
第?部 東日本大震災と仏教──仏道の現代的意義──
【基調講演】今、仏教に何ができるのか──被災地をめぐって──(大谷徹奘)
【講演1】岩手県陸前高田市における浄土真宗本願寺派の対人支援について(金澤 豊)
【講演2】宮城県名取市における浄土真宗本願寺派の対人支援について (安部智海)
【講演3】問われた我々の存在意義──天台宗防災士の誕生──(高見昌良)
【講演4】仏教徒として、今やるべきこととやっておくべきこと(森本公穣)
【パネルディスカッション】東日本大震災と仏教──仏道の現代的意義── (コメンテーター 若原雄昭)
楠 淳證[クスノキ ジュンショウ]
編集
内容説明
日本仏教研究の新視座。仏教学・法会学・歴史学・建築学などの幅広い視野より伝統ある「法会と仏道」の意義を明らかにするとともに、東日本大震災における仏教者(僧侶)の活動を通じて、仏道の現代的意義を問う。
目次
第1部 法会と論義(中世南都諸寺の法会―講説・論義・打集を中心に;法相論義と仏道―「一仏信仰」か「多仏信仰」か)
第2部 法会の空間(法会と講式―南都・北嶺の講式を中心として;歌人の儀式の『月講式』―鴨長明と道元における三界唯心;法会と仏堂)
第3部 僧の生活と持律(北嶺の戒律―実導仁空を中心に;南都の戒律―中世の復興から現代を考える;親鸞と戒律―無戒名字の比丘)
第4部 東日本大震災と仏教―仏道の現代的意義(基調講演 今、仏教に何ができるか―被災地をめぐって;講演1 岩手県陸前高田市における浄土真宗本願寺派の対人支援について;講演2 宮城県名取市における浄土真宗本願寺派の対人支援について;講演3 問われた我々の存在意義―天台宗防災士の誕生;仏教徒として、今やるべきこととやっておくべきこと;パネルディスカッション 東日本大震災と仏教―仏道の現代的意義)
著者等紹介
楠淳證[クスノキジュンショウ]
1956年生まれ。兵庫県出身。龍谷大学文学部仏教学科卒業、龍谷大学大学院文学研究科博士後期課程単位取得満期退学、龍谷大学専任講師、助教授を経て、龍谷大学教授、アジア仏教文化研究センター長。専門は仏教学、特に唯識教学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。